代表的な病気と治療について
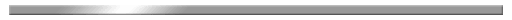
(2001/07/01作成)
内容
脳血管障害
脳動脈瘤の治療選択 −開頭術 VS 血管内治療ー (2003/05/12)
未破裂脳動脈瘤とその治療
破裂脳動脈瘤とその治療
虚血性脳血管障害
もやもや病とその治療
脳腫瘍
重粒子線治療とは (2003/09/08)
重粒子線治療が高度先進医療に (2003/22/04)
脳下垂体腫瘍とその治療
髄膜腫とその治療
転移性脳腫瘍とその治療
聴神経腫瘍とその治療
その他の疾患
三叉神経痛
顔面痙攣
その他の話題
痴呆 ーアルツハイマー病に環境要因の関与もー (2002/08/07)
日本循環器学会が一般人の除細動器の使用解禁を提言 (2003/02/05)
人工栄養は緩和ケアでないと尊厳死認める (2003/06/26)
新しい定位放射線照射装置 サイバーナイフ (2002/05)
脳外科手術(開頭術)の合併症について
トップページに戻る
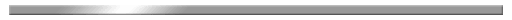
脳血管障害
脳動脈瘤の治療選択 −開頭術か血管内治療か 国際試験結果が引き金ー (03/05/12)
昨年英国でくも膜下出血に対する両治療法の有効性を比べる世界初の国際破裂脳動脈瘤臨床試験(ISAT)が行なわれた。対象は比較的軽いくも膜下出血で、どちらの治療でも適応できる2000例を無作為に2分し、それぞれの経過を比べた。治療1年後に、重い障害が残って介護が必要になったり、死亡した割合を調べたところ、開頭術で30.6%、血管内治療で23.7%だった。
手術と遜色(そんしょく)ないばかりか、有効性や安全性で優れていることが判明した。日本では血管内治療は開頭術の年間約2万5000件に対し約3000件と1割強にとどまっている。1997年に保険適用されているが、日本脳神経血管内治療学会が認定した指導医・専門医は約160人と少ない。しかし、ISATの結果、欧州では血管内治療が50%から70%に急増、今後、血管内治療を選択することが国際的な流れになるとみられている。将来は血管内治療が30〜40%を占めると見込まれる
ただ、ISATスタディーに疑問を呈する脳神経外科医も多く、再出血率は血管内治療が若干高めで、再破裂防止の点では開頭術が優れているとしている。
コメント・関連情報
ここで発表された治療成績を普遍的なものとして本邦にもあてはまるものとするのには大きな疑問があります。本邦や米国と異なる英国や欧州の医療体制に由来するバイアスが影響しているという評価が妥当です。本邦は脳神経外科治療施設や救急体制が(英国と比較して)充実し、軽症例の治療成績は発表された結果よりもはるかに良好です。
くも膜下出血の治療は、開頭術と血管内治療とに分けられる。 開頭術はクリップで動脈瘤の頸部を挟んで出血を防ぐ方法(クリッピング術)。30年以上改良されつつ施行されてきた方法で、長所(高い出血の根治度、血管壁の外から視覚的に血管病変を確認する利点、多様な治療オプションなど)や短所(開頭術にともなう侵襲性など)が周知されている。血管内治療は、脳に直接触れることなく、先端に細いコイルのついた管(カテーテル)を太もものつけ根の動脈から血管内に通し、カテーテルで動脈瘤の内部にコイルを詰めて出血しないように脳のこぶをふさぐ方法。これまで血管内治療は手技者の技術訓練が必要であるとともに、「血管内治療は道具に依存する割合が高いが、機器がまだ発展途上」であることから、患者の意識状態が不良、脳動脈瘤の位置的に開頭術が困難、開頭術のできない重症例は高齢者などの症例における代替的処置とみられてきた。最近は機器の開発も進み、発足した血管内治療学会も認定制度を作成して治療成績の向上を目指している。
内容(目次)へもどる
未破裂脳動脈瘤とその治療
1、未破裂脳動脈瘤の特徴
脳動脈瘤は1-2 %の頻度で存在し、1年にその内の約2 %が破裂してクモ膜下出血あるいは脳内出血を起こすとされています。動脈瘤の直径が5mm以上、形が不整、家族歴がある場合などでは破裂する可能性が高いことが判っていますが、どの動脈瘤が破裂するかを特定するのは困難なため、出血の予防が大切です。
2、脳動脈瘤の発生・増大・破裂(クモ膜下出血)について
脳動脈壁の弱い部分に、遺伝要因や高血圧などが原因で“こぶ(脳動脈瘤)”が発生します。ゴム風船のように増大し動脈瘤壁が薄くなり、急激な血圧上昇が契機となって破裂します。いったん破裂すると約1/2が死亡、1/4が後遺症を残して生存し、社会復帰できるのは残りの約1/4のみです。
3、動脈瘤の治療
薬物などによる破裂予防は困難で、下記の治療が行われます。一般に全身麻酔が危険な場合や特殊な部位の動脈瘤(脳底動脈瘤など)を除いてクリッピング術が採用されており、当院でもこれに準じた治療をしています。
動脈瘤クリッピング術
全身麻酔下で開頭・顕微鏡手術をおこない、金属製クリップで動脈瘤を処理します。この治療法には長い経験があり、手術中に起こりえる問題にすぐに対応できます。死亡率は1%以下、合併症率は4%以下(後述)です。
動脈瘤塞栓術
脳動脈に入れたカテーテルから動脈瘤の中にコイルを入れてパッキングする新しい方法です。開頭なしで行える利点がありますが、長期成績が不明なこと、操作中の事件(破裂など)の処理が困難であるなどの課題があります。
4、未破裂脳動脈瘤の手術適応
今までに報告されたデータを総合して、“日本脳ドック学会”は以下のガイドラインをまとめました。私達もこの原則に則っていますが、個々の患者さんの多様性(活動度、家族歴など)に柔軟に対応する必要もあると考えています。
1、年齢は原則として70歳以下
2、心肺等に重篤な合併症がない(麻酔の安全性への配慮)
3、脳に虚血性変化が少ない(開頭術の安全性への配慮)
4、動脈瘤の直径は原則として5mm以上
5、治療の効果とリスクとに関する同意(インフォームドコンセント)が得られる
内容(目次)へもどる
破裂脳動脈瘤とその治療
原因と症状
脳血管に出来た動脈のコブ(動脈瘤)が破裂しておこります。突然に激しい頭痛が襲い、嘔吐あるいは気を失い倒れることもあります。強い頭痛でも電気が走るように一瞬で無くなってしまうのは多くの場合神経痛です。
家庭での処置
側臥位で頭を横にして、吐いた物がのどを詰めない様に、また呼吸が楽にできるようにします。後はあまり刺激せずに(血圧が上がります)救急車を呼ぶだけです。
予後
動脈瘤はいったん出血すると約50%が死亡、25 % が社会復帰、25 % が種々の程度の後遺症を残します。脳動脈の血管壁の弱い部分に発生した脳動脈瘤は5〜6mmに膨らんでその壁が薄くなると、急激な血圧上昇などがきっかけで一気に膨らみ破裂すると考えられています。出血が少量であれば頭痛だけで、大量に起これば即死に近い状態となります。運良く最初の出血を克服した患者さんに、次のような3つの病態が続いて起こります。
再出血:出血が止まった脳動脈瘤は非常に破裂し易い状態で、何度も破裂することがあります。“崖っぷちで堪えている患者さんをけり落とす”ように例えられています。
脳血管攣縮:血管周囲に付着した血液が脳血管を細くする現象して脳梗塞を起こします。確実な予防法や治療法はまだありません。
正常圧水頭症: 痴呆 、尿失禁 、歩行障害などを起こしますが、簡単な手術で改善します。
治療
治療の目的は、再出血の予防、周囲の血腫を除去して血管攣縮を予防することです。治療法には動脈瘤を外側から観察してクリップで血流を遮断する方法(開頭術、顕微鏡手術)と、動脈に入れたカテーテルでプラチナ製のコイルを動脈瘤の中に充満させる方法(血管内治療、コイル塞栓術)とがあります。開頭術による動脈瘤クリッピングは長い歴史があり長期成績も明らかで、さらに術中の不測の事態(出血など)に対応できるため、私を含め多くの施設で第一選択にしています。血管内治療も技術・材質の向上が著しく、高齢者、重症例、手術困難な部位、全身麻酔困難例などを治療しています。
内容(目次)へもどる
虚血性脳血管障害
1、発症と診断
頚部や頭部の血管が細かったり(狭窄)詰まったり(閉塞)すると、脳血流が減少して、手足の運動麻痺や感覚異常(しびれ)、喋れない・言葉が理解できない、眼が見えない(一側盲あるいは視野障害)などの症状が、数分から数時間起こって消失したり(一過性脳虚血発作)あるいは回復せずに後遺症として残ったりします(完成卒中)。このような場合には急いで脳神経外科あるいは神経内科を受診して下さい。病院では、外来検査で脳梗塞の有無(MRI)と脳血管の病変の有無(MRA)を検査できます(20分程度)。最近では脳梗塞を早期に発見できる特殊な撮影方法もあります。
2、治療
治療の目的は、回復不可能な脳梗塞への進行を予防すること、少しでも症状の改善を図り後遺症を少なくすること、脳浮腫などを治療して生命を助けること、にあります。
内科的治療
症状が一時的で脳血管の病変(狭窄、閉塞)が認められない場合には、薬物治療を中心とする内科的治療を行います。
外科的治療
脳血管に病変(狭窄、閉塞)が認められる場合には症状が急激に悪化する可能性があるため、入院して薬物治療を開始するとともに外科治療が必要か否かを検討します。
(1)頚動脈病変の外科治療
頚部の頚動脈の動脈硬化性狭窄性病変は、手術が安全で薬物治療単独よりはるかに予防効果が優れていることが証明されています。幾つかの工夫が必要ですが、手術時間は2ー3時間、合併症は3ー4%以下とされています。
(2)頭蓋内血管病変の外科治療:脳血流が低下している場合には高頻度に再発がみられるため、脳血流を増加させるバイパス術が勧められます(現在この効果を確認する臨床研究が全国規模で進められています)。また最近はカテーテルを用いた急性期の血行再建治療が、発症からの数時間以内で重症度や脳血流などの条件を満たす患者さんに行われています。 (010605
作成)
内容(目次)へもどる
もやもや病とその治療
1、もやもや病とは
もやもや病は脳底部の主幹動脈が狭窄したり閉塞して血流不足を起こし、これを補うため新しい血管網が発達し、これが脳血管撮影検査で煙のようにもやもやと見えるため “もやもや病” という病名がつきました。原因は不明で難治性疾患に指定されていますが、一部に家族性の発生を認めます。この病気は子供に起こり易く、一過性の脳虚血発作、さらに進行して多発性脳梗塞,脳委縮を起こし、後遺症を残します。また成人ではもやもや血管から脳出血を起こすことがあります。今回あるいは今後起こるかもしれない症状に、その都度適切な治療が必要とされる、長期的な病気と捉える必要があります。
2、治療
原因が不明であるため、もやもや病を完全に治癒させることはできず、進行を予防するのが採るべき治療となります。このために、脳の血管や血流の検査をして、適切な血行再建術を行います。この方法として、頭皮を栄養している浅側頭動脈と脳の表面を走る中大脳動脈の分枝と直接吻合する浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術、側頭部の筋肉を脳表に接触させてその間の血管造成を図る間接的な吻合術があります。また手術後も、定期的に脳血流や血管の検査をしたり、場合により服薬する必要があります。
3、血行再建術の合併症について
麻酔方法、手術操作、薬物内容などに関して最大限に工夫しますが、手術に関連してこのような合併症が起こりうることを理解いただくため、ここに説明します。
1)手術中・手術後の脳梗塞
もやもや病の患者さんは既に脳血流が低下しており、また脳血管は血圧・血液ガス成分などの変化に非常に敏感です。このため術中・術後のわずかな変化が原因で脳梗塞が発生することがあります。
2)後出血
手術中に完全に止血するように努めますが、その止血が不充分であったり血圧が上昇して手術後に頭蓋内出血を生じる場合があります。また虚血状態に陥っている部分の血流量が急激に増加することが原因で出血する可能性もあります.
3)創部の癒合不全や脱毛
本来頭皮を栄養する浅側頭動脈を使用するため、頭皮組織の血流が悪くなり、頭皮の壊死・脱毛などの美容上の問題を生じる可能性があります。
4)感染
創部から細菌が入って感染を起こす場合があります。抵抗力が弱かったり,抗生剤の効果が乏しく感染が深部に及ぶと術後,細菌性髄膜炎や脳炎など深刻な感染性合併症を生じる可能性があります. (2001/08/01))
内容(目次)へもどる
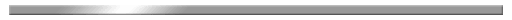
脳腫瘍
文科省、重粒子線治療の小型化で普及をはかり、全国に整備を (03/09/08)
1、重粒子線がん治療装置とは
独立行政法人放射線医学総合研究所(千葉市)が世界で初めて開発した医療用重粒子加速器。炭素イオンをシンクロトロンで光速の84%まで加速して患部に照射する。周辺の正常組織への影響が少ないのが特徴。早期の肺がん、肝臓がん、前立腺がん、脳腫瘍、鼻腔がんなど、がん全体の約5%が対象。白血病や、動きのある胃や腸のがんは適応外。
2、重粒子線がん治療装置の特徴
1994年に臨床試験を開始し、これまでに約1600人の患者を治療。初期の肺がん患者で、高齢などで手術が不可能な患者に施した場合の5年生存率は42%。放射線治療の同22%のほぼ倍だ。前立腺がんでは、手術例より7-10%も5年生存率が高い。照射技術の向上とともに、現在は肺がんでわずか一回、肝臓がんで二回の照射となっている(一回1-2分)。前立腺がんは今の段階では20回の照射が必要だ。副作用がない上、麻酔も不要。今後、さらに照射技術が向上して各地に普及すると、日帰り治療も可能となり、多くの人が軽い負担で治療を受けられることになる。
3、問題点とその対策
加速器やシンクロトロンなど大規模な装置が必要で建設費は320億円もかかる。現在あるのは放射線医学総合研究所と兵庫県立粒子線治療センターだけ。文部科学省は本年から2年間で規模を約3分の1、建設費を100億円以下にするための技術を開発する。国立がんセンター東病院や群馬大病院、横浜市立大病院、九州大病院などで建設の意向。
内容(目次)へもどる
重粒子線治療、一部保険を認め高度先進医療に (03/11/04)
厚生労働省は放射線医学総合研究所(千葉市)が申請していた重粒子線を使ったがん治療を、厚生労働省が高度先進医療に承認、11月1日から一部の費用が保険適用になった。 対象は肺がん、頭頚部がん、前立腺がん、骨・軟部組織がんの四種類で、転移のないもの。診断、検査、投薬、入院費用は健康保険が適用され、一連の重粒子線照射の費用314万円が患者負担となる。
重粒子線は放射線の一種。治療では、重粒子の一つの炭素イオンを大型加速器で光速の約84%の速度にして患部に照射する。体の奥のがん細胞に強く作用し、ほかの放射線治療に比べ、皮膚などの正常細胞を傷つけることが少ないとされる。重粒子線治療装置について、文部科学省は普及を目指し、装置を小型化、低コスト化する開発を来年度から始める。一部保険適用の対象となったことで、弾みがつきそうだ。
同研究所は1994年の臨床試験開始以来、約1600人の患者に実施、手術をした場合と同等の成績を挙げている。今後、がんが骨に浸潤して手術は危険が伴う患者や、手術すれば歩けなくなるなどの副作用が出る患者を中心に、年間300人程度を受け入れる方針。
内容(目次)へもどる
脳下垂体腫瘍とその治療について
1、下垂体腫瘍とは
脳下垂体という部分に発生した腫瘍で、脳腫瘍全体の約15%を占めます。脳下垂体は6種のホルモン(成長ホルモン、乳汁分泌ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、性腺刺激ホルモン、抗利尿ホルモン)を産生しています。この部分に腫瘍が発生すると、ホルモンの産生低下による症状(下垂体機能低下症状)、ホルモンの過剰による症状、周囲の神経組織を圧迫することによる視力・視野障害、などが起こります。脳下垂体自体から発生した良性腫瘍(下垂体腺腫)がほとんどですが、その他の腫瘍(頭蓋咽頭腫,髄膜腫,胚細胞腫,ラトケ嚢胞,類上皮腫,脊索腫,下垂体膿瘍など)もあります。
2、治療について
良性の腫瘍でもやがて大きくなって、新しい症状の出現や既にある症状の進行が予想されます。また大型化すると治療が困難になったり後遺症が残る可能性があります。
内服薬(パーロデル)や放射線治療(ガンマナイフという特殊な放射線治療も含めて)が適用となる下垂体腫瘍もありますが、安全に摘出できる可能性が高い場合には下記の手術による摘出術が一般的な治療法です。
3、経鼻的下垂体腫瘍摘出術
上唇の裏側を3cm切開して鼻腔および副鼻腔を経由する方法です。自然にある空洞を利用し、また脳に触れないで腫瘍を摘出するため、危険が少ないという特徴があります。手術後の2−3日は鼻腔にガーゼを詰めるため、口から呼吸をしてもらいます。場合によっては下腹部や大腿部から脂肪や筋肉片を摘出して手術部に充填することがあります。
4、経鼻的下垂体腫瘍摘出術による合併症について
起こりうる合併症を述べますが、手術前後の管理や術中の工夫により起こることは稀です。また起こっても多くの場合は対処可能です。
4−1、髄液鼻漏
脳の周囲に存在する髄液が手術部から鼻に漏れる(髄液鼻漏)ことがあります。放置すると髄膜炎などの感染症が起こる可能性があります。対策としては、手術中に確認されれば脂肪や筋肉片を充填し、また術後では腰部から髄液を抜くなどの治療をします。
4−2、感染
手術部分に化膿が起こる可能性があります。
4−3、尿崩症
尿量を減らすホルモン(抗利尿ホルモン)が減少して、尿量が異常に増加することがあります。多くは一時的でおさまります。
4−4、脳下垂体機能低下
ホルモンが減少して種々の症状がでることがあります。ホルモン剤の投与が必要になります。
4−5、その他
上唇の一部のしびれ感、鼻の不快感や乾燥感などがしばらく続くことがあります。
内容(目次)へもどる
髄膜腫とその治療
1、髄膜腫とは
頭蓋骨の内側で脳を包んでいる膜(髄膜)から発生する腫瘍です。全脳腫瘍の約20%を占め、その大部分が良性です。緩徐に増大して、頭痛や脳の圧迫による種々の症状(圧迫される部分により、運動障害・けいれん・知覚障害・視力視野障害・精神症状など)を起こします。圧迫がさらに強くなると生命に危険が及びます。
2、治療法
すでに症状があるか偶然発見された無症候性の腫瘍か、腫瘍の発生部位と大きさ(将来症状が起こる可能性や摘出の困難性に関連します)、年齢(期待される生存期間中に症状がでない可能性、全身麻酔の安全性などに関連します)などにより治療法が選択されます。
1)経過観察
定期的に画像検査をして腫瘍の増大を観察する方法です。高齢者で無症候性の小さい髄膜腫などが該当します。
2)開頭術による摘出術
全身麻酔下で腫瘍を摘出する方法です。短時間で完全治癒(完全摘出)が期待できる、腫瘍が一部残っても症状の改善が期待できる、腫瘍の正確な診断が得られ今後の予測ができる、などの利点があります。従って、すでに症状がある大型腫瘍の場合、無症候性であるが完全治癒の意義が大きい若い患者さんの場合などが該当します。
3)定位放射線手術
多数の放射線ビームを腫瘍部分に集中して腫瘍を壊死させます。数ヶ月の経過で腫瘍の増大の停止や縮小が見られます。頭部の侵襲的固定が必要か(ガンマナイフ装置)不必要か(サイバーナイフ装置)の違いはありますが、全身麻酔が不要で短時間で治療が終了し、周囲の神経組織を障害する危険が著しく少ないため、高齢者、中―小型の腫瘍、摘出術が困難な腫瘍などが該当します。
3、開頭術による摘出術の合併症について
開頭術で起こりうる合併症については別項で説明します。ここでは髄膜腫の手術で起こり易い合併症に焦点を絞って説明します。
1)脳内出血や脳腫脹
長期にわたる圧迫を手術により急激に解除するため、脳内の血流や圧力が変化して脳出血や脳腫脹が起こることがあります。これが予想される場合には頭蓋骨を入れないで手術を終了する事もあります。
2)手術前の症状が増悪する場合があります(多くの場合一時的ですが)。
3)腫瘍が硬膜や頭蓋骨に浸潤していると、腫瘍の摘出後に代用の硬膜や骨を使用します。このような場合に強い感染が起こると、代用材料を除去する必要があります。 (2001/08/01)
内容(目次)へもどる
転移性脳腫瘍とその治療
1、転移性脳腫瘍とは
転移性脳腫瘍は、他の体の部位に存在する癌が脳内に運ばれて大きくなったものです。最近は肺癌,乳癌(原発巣と言います)からの転移が多く、全脳腫瘍の15%を占めます。悪性腫瘍ですから、出血したり急速に増大して、脳局所の症状や痙攣を起こし、さらに増大すると頭蓋内の圧力(脳圧)が上がって頭痛や意識障害を起こし、やがて生命が危険となります。
2、治療について
転移性脳腫瘍は一般的に予後不良で、治療の目的は長期の生存を期待することではなく、患者さんの激しい頭痛や重篤な症状を軽くして生活の質を高めることです。腫瘍の新たな発生や再発の可能性や、頭部の治療が成功しても原発巣や他の転移巣の状態で悪化する可能性があるなど、脳原発の脳腫瘍の“それが治癒したら完全治癒”とは異なる背景があります。
1)定位放射線手術(サイバーナイフやガンマナイフなど)
放射線のビームを腫瘍部分に集中させて壊死させる治療法で、最新のサイバーナイフでは侵襲的頭部固定が不必要で分割照射も容易になりました。開頭術をしなくてすむのが最大の利点ですが腫瘍が縮小するまでに数ヶ月を要するため、小型腫瘍(3cm
以下)、手術が困難な部位や多発性の場合などが適しています。本治療法の詳細は別項で説明します。
2)開頭術
全身麻酔下で開頭し腫瘍を摘出します。出血した腫瘍での緊急手術、急いで減圧を必要とする大型腫瘍(3cm
以上)で、単発腫瘍の場合、あるいは多発腫瘍でも一回の手術で摘出できる場合が適応となります。
3)薬物療法(抗癌剤)、免疫療法
一部の腫瘍を除いて有効性が乏しいとされています。
3、開頭術による腫瘍摘出術の合併症
開頭術で起こりうる合併症については別項で説明し、ここでは転移性脳腫瘍の手術に特異的な合併症について説明します。
1)頭蓋内出血と脳浮腫
転移性腫瘍は脆弱な血管に富んでおり、また腫瘍周囲に強度の脳浮腫をともないます。手術後にわずかに残存した腫瘍から出血する可能性や、脳浮腫が増悪する可能性があります。これによる症状が強い場合には再手術が必要となります。
2)腫瘍播種
手術を契機に脳内に癌が拡がる(播種)場合があり、急速に拡大して治療が困難になることがあります。
3)他臓器の悪化
脳腫瘍が摘出できた場合でも、手術を契機に他臓器に顕在あるいは潜在していた病巣が増大して悪化することがあります。 (2001/08/01)
内容(目次)へもどる
聴神経腫瘍について
1、聴神経腫瘍とは
聴神経腫瘍は聴力や平衡感覚に関連する聴神経にできた良性脳腫瘍です。めまい・難聴、顔面の運動障害、歩行障害、さらに大きくなると激しい頭痛や意識障害をきたします。
2、治療法
すでに症状がある場合には腫瘍体積を短時間で減らすことができる開頭手術が一般的で、症状がまだ出ていない(無症候性)場合には開頭手術以外の方法も選択の余地があります。
1)経過観察
高齢者で無症候性の小さい腫瘍では、定期的に腫瘍の大きさを観察する場合もあります。
2)開頭術による摘出術
全身麻酔下で腫瘍を摘出する方法です。完全治癒あるいは腫瘍が残存しても症状の改善が期待できる、腫瘍の正確な診断が得られる、などの利点があります。すでに症状がある大型腫瘍の場合、無症候性であるが完全治癒の意義が大きい若い患者さんの場合などが該当します。
3)定位放射線手術(サイバーナイフやガンマナイフなど)
多数の放射線ビームを腫瘍に集中して腫瘍を壊死させます。数ヶ月の経過で腫瘍の増大の停止や縮小が見られます。全身麻酔が不要で短時間で治療が終了し、周囲の神経組織を障害する危険が著しく少ないため、高齢者、中―小型の腫瘍、摘出術が困難な腫瘍などが該当します。
3、開頭術による摘出術の合併症について
開頭術で起こりうる合併症については別項で説明します。ここでは聴神経腫瘍の手術で起こり得る合併症に焦点を絞って説明します。
1)脳神経麻痺
腫瘍のそばには聴力、顔面の動き、飲みこみ、顔面の感覚などに関係する聴神経、顔面神経、下位脳神経、三叉神経があります。これら神経は圧迫され脆弱になっているため、手術操作で神経の働きが低下したり消失したりする可能性があります。
2)髄液漏
開頭部の頭蓋骨には耳や鼻に連絡している空洞があり、また脳はきれいな液体(髄液)で囲まれています。この空洞が開頭時に開放されたままになると髄液が耳や鼻に漏れ(髄液漏)、さらには感染症(中耳炎や髄膜炎など)が生じることがあります。術中の予防や早期発見で治る場合がほとんどですが、まれに再開頭が必要な場合もあります。
3)脳幹損傷
腫瘍が大きく生命や意識の中枢である脳幹への圧迫が強い場合には、脳幹の障害により意識障害や呼吸・血圧異常などの重篤な状態が起こりえます。
(2001/10/01)
内容(目次)へもどる
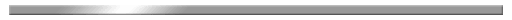
その他の疾患
三叉神経痛
1、三叉神経痛とは
顔面の片側―特に唇の周囲、あるいは唇と頬あたりーに電気が走るような激痛が生じ年々強くなるのがこの痛みの特徴です。三叉神経が脳から出る部分で動脈や静脈に圧迫されて異常反応を起こすことが原因です。
2、治療法
1)内服薬による治療
抗てんかん薬のテグレトールを服用しますが、効果が減少したり、薬量を増やすとふらつきが起こるため、これだけで完治させるのは困難です.
2)神経ブロックによる治療
一時的あるいは永久的に神経を麻痺させます.顔面のしびれが残り,また別の顔面痛が起こる場合があり、手術困難な場合の治療と考えられています.
3)手術による治療
耳介の後ろから開頭して脳血管の圧迫を取る方法で、原因を除去する合理的な治療法です。90から95%の患者さんが重大な合併症を生じることなく,術後完治(痛みの長期の完全消失)しています。
3、外科的治療法(神経血管減圧術)の合併症
開頭術一般の合併症については別項で述べ、ここでは本手術に特異的な合併症につき説明します。
1)難聴,耳鳴り:三叉神経は聴力や平衡機能と関係する神経の近くにあります。このため難聴,耳鳴りなどが起こる可能性があります.
2)髄液漏:脳が浮いている髄液が、手術でできた骨の孔を通じて鼻や耳に漏れて(髄液漏)、中耳炎や髄膜炎などの感染を起こす可能性があります。
3)その他:血管の圧迫部位は深部で意識に関係する脳幹という部分にあります。ここを損傷して重い後遺症を残したり死亡したという報告もありまガ、種々の工夫により現在までにそのような例は経験しておりません。 (010604作成)
内容(目次)へもどる
顔面けいれん
1、顔面けいれんとは
一側の顔面が不随意にピクピクと動いてしまう病気です。脳深部の動脈の曲がりが強くなり顔面神経を圧迫し、異常に興奮させることが原因です。放置しても命を危うくすることはありませんが、数年の経過で眼の周囲から口角さらには頚部に拡がり、進行すると眼が開き難くなったり、顔面の麻痺が起こります。
2、治療法について
1)内服薬
抗てんかん薬や安定剤などを用いますが、効果はあまり期待できません。
2)神経ブロック
麻酔薬や神経毒素を局所注射して異常興奮を抑える方法です。有効期間が短く、また顔面神経麻痺が起こる場合もあります。
3)開頭手術による治療
全身麻酔下で耳介後部に直径3cmの開頭を行い、原因となっている脳血管を移動させて顔面神経への圧迫を除去します(神経血管減圧術)。原因を取り除く合理的な治療で、90-95%の患者さんが合併症なく完全治癒します。
3種類の治療がありますが、完全治癒を希望される患者さんには手術が、高齢の患者さん・全身麻酔が危険な患者さんには内服や神経ブロックが勧められます。
3、外科的治療法(神経血管減圧術)の合併症について
脳腫瘍や脳動脈瘤などの開頭術と比べ,一般に危険性は低いと考えられます。ここではこの手術に特有な合併症の可能性を説明し、開頭術一般の合併症の説明は別の項で述べます。
1)難聴、耳鳴り
顔面神経は、聴力や平衡機能に関連する聴神経と近接しています。この神経は圧迫などに弱いため、術後に難聴・耳鳴りが起こる場合があります。なかでも高齢者の患者さんに起こりやすいとされており、繊細な手術操作やモニタリングで予防します。
2)髄液漏,中耳炎
開頭部の頭蓋骨には耳や鼻に連絡している空洞があり、また脳はきれいな液体(髄液)で囲まれています。この空洞が開頭時に開放されたままになると髄液が耳や鼻に漏れ(髄液漏)、さらには感染症(中耳炎や髄膜炎など)が生じることがあります。術中の予防や早期発見で治る場合がほとんどですが、まれに再開頭が必要な場合もあります。
3)深部脳幹近くの操作に関連して
本手術は生命や意識の中枢である脳幹表面で行います。血管の捩れや小血管の損傷による脳梗塞、脳幹への圧迫による出血などの合併症が報告されています。これが生じる可能性は著しく低い私は経験してもいませんが、いったん生じた場合には重篤な状態になりえます。(2001/08/01)
内容(目次)へもどる
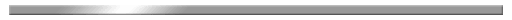
その他の話題
アルツハイマー病に環境要因の関与も (02/08/07)
この病気の初期には短期記憶障害と場所や日付が分からなくなる見当識障害が、進行するとすべての精神機能が低下する。1993年、「アポリポタンパクE」というアルツハイマー病の危険因子が発見され、遺伝的要因によって発病するとされた。しかしその後環境因子の関与が示唆されてきた。
人種的にアルツハイマー病になりやすい遺伝的素因を多く持つアフリカ出身者を対象に行われた昨年の米国の研究によれば、アフリカ在住者と米国在住者の発症率は米国在住者の方が2.5倍も高いと判明した。さらに血管因子の関与に関するフィンランドの報告では、中年期に高血圧やコレステロール血症があると、老年期にアルツハイマー病になりやすいという結果がでた。ロッテルダムで約2万人を2.5年追跡した食事因子の関連調査では、魚の摂取が発症の抑制因子になるという。不飽和脂肪酸、ビタミンC、Eやミネラルなどが良いと推定されている。
コメント
“痴呆”には多くの原因があります。狭義の痴呆はアルツハイマー病や脳血管性痴呆などですが、これらは現在のところ治癒困難で、見守り(介護)の対象です。しかし、他の原因なのに、“痴呆”症状を呈しているため治癒困難とされている人たちがいます(正確な数は不明です)。この場合の原因は、精神科や神経内科が担当する老人性うつ病、脳神経外科が担当する慢性硬膜下血腫や正常圧水頭症、さらに家族や地域における会話や人的交流不足に由来する活動性の低下、などです。
まず神経内科で脳の検査を勧めます(痴呆の評価、MRI検査や脳血流検査など)。さらに痴呆を(も)対象とした介護施設に相談することを勧めます。デイケアーなどを受けて、症状が軽快する場合も認められます。
内容(目次)へもどる
日本循環器学会が一般人の除細動器の使用解禁を提言、厚労省が迅速な対応 (03/02/05)
心室細動は致死性の不整脈で、毎年心肺停止で搬送される約8万人の患者の半数近くが心臓に原因があり、その多くが心室細動を起こしているとされています。日本循環器学会は平成14年12月10日、除細動器を空港や駅など公共性の高い場所に設置し、一般の人も使用できるよう段階的に使用条件を緩和することを厚生労働省に提言しました。
除細動器の使用は、医師と医師の指示を受けた看護師・救急救命士にしか使用が認められていないのが原則です。 01年10月から日本航空国際線で乗務員が除細動器を使用しても医師法などに違反しないとされ、また03年4月から救急救命士は医師の指示なしで使えるよう整備が進んでいます。米国で空港に設置し一般の人が使用、救命効果を上げています。
学会はこうした状況を踏まえ(1)看護師や救急救命士、救急隊員、消防士などによる医師の指示なし使用、(2)一般の人が除細動器を使えるための講習制度など環境整備、(3)航空機や客船、新幹線、空港、駅、学校、競技場など公共性の高い場所への除細動器の設置、を求めました。
これに対して、厚生労働省は緊急避難的に一般の人が使っても医師法などに違反しない、「駅や空港、乗り物、競技場など公共の場所に除細動器を置くこと自体は問題ない、一般の使用は個別判断になるが緊急性が認められれば法律違反にはならない(医事課)としました。同学会によると、倒れた人の体に電極をつけ、音声に従ってボタンを押すだけで簡単に使える自動体外式除細動器(AED)が開発されているとのことです。
コメント
心拍を調節している心臓の一部が心筋梗塞などで傷つき、その結果起こる無秩序な調子取りによって心臓がポンプ機能を失った状態を心室細動といいます。除細動とは電気ショックで心室細動を止めて、正常な心臓機能を回復させる治療です。ポンプ機能を失っている間は心臓マッサージと人工呼吸を行います(マッサージは毎分約150回、これと人工呼吸の比率は
15:2 が勧められています)。
内容(目次)へもどる
人工栄養は緩和ケアではないと尊厳死認める (2003/06/29)
オーストラリアのビクトリア州最高裁は03/06/29、末期の女性患者(68)にチューブで人工栄養を与える医療行為は「患者の苦痛を和らげる緩和ケアには当たらない」とし、人工栄養を中止して尊厳死させたいとする家族の訴えを認める判決を言い渡した。
患者の女性は老人性痴ほう症。8年前から人工栄養を受け、ここ3年は植物状態で回復が見込まれない状態。家族は人工栄養のチューブを取り外すよう病院に求めていた。ビクトリア州の法律では、患者は望まない医療行為を拒否する権利を持つが、医療機関が「緩和ケア」をやめるのは違法としている。尊厳死に否定的なカトリック教会などは、人工栄養が「緩和ケア」に当たると主張していた。(シドニー共同)
コメント
植物症、緩和ケア、経管栄養治療、尊厳死など、複雑な問題を含む話題です。患者・家族の意向が最重要ですが、これが社会の倫理・法律に一致しない場合も時にあります。担当医師の裁量権も時代とともに変化しつつあり、真摯な医師ほど悩む場面が多くなっています。
内容(目次)へもどる
新しい定位放射線照射装置 サイバーナイフ (2002/05)
1、サイバーナイフとは
サイバーナイフは、細いX線ビームを病変に集束するように照射して、腫瘍や血管奇形などを治療する定位放射線照射システムです(写真1)。新しい機構を取り入れて、優しく正確な治療ができるようになりました。このサイバーナイフが、私の勤務する蘇生会総合病院に日本では7番目(関西では大阪大学についで2番目)に稼動始めました。3月初旬に症例数が多い岡山旭東病院で同装置の勉強をしてきました。放射線治療医は脳神経外科医と異なり、安全性に優った分割照射を頻用しているのが印象的でした。
2、サイバーナイフの特徴
A、マスクにより頭部を固定します(写真2)
自動的に頭部の動きを補正するため、頭蓋骨ピン装着(写真3)は不要となりました。
B、一回照射も、分割照射もできます。
簡便なマスク固定により分割照射も容易で、大型病変・重要組織近くの病変を安全に治療できます。
C、耳鼻咽喉、口腔、頸椎などの治療も可能です
頭蓋内病変に限られていた治療範囲が拡大しました。
D、複雑な形をした病変でも正確に治療できます。
X線ビームの照射の自由度が高いため、複雑な病変でも均一な線量分布が得られます。
3、代表的病変
転移性脳腫瘍は、局所制御率が約90%と非常に有効です。聴神経腫瘍も局所制御率が良好で聴力温存は70-80%、顔面神経機能は95 %以上で保存されます。髄膜腫、脳動静脈奇形にも有効です。
4、副作用、合併症
早期(数日以内)では、吐気・嘔吐(10%程度)、発熱や痙攣など、数週間から数ヶ月では腫瘍周囲の浮腫、脱毛、脳神経障害など、数ヶ月から数年では腫瘍周囲の壊死や血管閉塞、腫瘍新生などが知られています。



写真1 ロボット 写真2 マスク 写真3 頭蓋骨ピン
内容(目次)へもどる
脳外科手術(開頭術)の合併症について
お腹の手術を開腹術、心臓や肺の手術を開胸術と言うように、脳に関連した手術を開頭術と言います。ここでは開頭術をした時に起こりえる変化と、それにより生じる症状(合併症)について述べます。あくまでもこのような可能性があるということで理解して下さい。特殊な手術部位や方法の場合にしか起こり得ないような合併症については別途説明します。 (01/06/04 作成)
感染
手術に由来する化膿です。頭皮や筋肉の部分における感染ではさほど問題はありません。深部に波及して頭蓋骨の中に達すれば髄膜炎や脳炎など深刻化する可能性があります。頻回の術野の洗浄や抗生物質の使用で、抵抗力が著しく低下していない通常の患者さんでは、感染症は最近まず経験していません。
出血
術中の止血が不充分であったり、術後の異常な血圧上昇などが原因で、頭蓋内に血腫ができる可能性があります。大きくなって脳を圧迫する場合には再手術が必要となります。術中のていねいな止血操作や予防的な止血剤の投与などで、最近はこの合併症も経験しておりません。
脳浮腫
術中の脳圧迫や重力による脳の捻れなどが原因で、脳が張れることがあります。抗脳浮腫剤などで予防します。
脳梗塞
血管内壁にある動脈硬化片や血栓などが剥がれ、下流の血管を閉塞して脳梗塞を起こすことがあります。ていねいな血管操作や血液凝固防止剤などで予防します。
これらにより発生する可能性がある症状(合併症)
上記の病態が発生して進行すると、手足の運動麻痺や感覚異常、ケイレン、意識障害などの症状が現れることがあります。多くの場合一過性で回復しますが、症状が残ったり(後遺症)生命が危険になる可能性も全く無いわけではありません。また脳の左側(優位半球と言います)に合併症が起こった場合には、言語障害や高次脳機能障害(記憶障害、計算力低下など)が起こる可能性があります。
合併症への対応
合併症を予測して、これが発生した場合には早期に発見する目的で、術後は集中管理部(ICU)で1時間毎に神経症状や全身状態を調べます。必要な場合には緊急検査を行い、24時間治療ができる体制をとっています。また翌朝にはCT検査をして異常が無い事を確認します。
内容(目次)へもどる)
トップページへもどる


