最新医学・医療
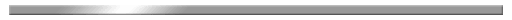
(2001年7月1日作成 2004年3月1日第1回改訂)
内容
低侵襲撃医療
日本におけるサイバーナイフ治療、稼動中止(平成14年末)と再開の動き(2004/02/01)
九州大学、国内初の“虚血性心疾患に超音波衝撃波治療” (2003/01/00)
最新の定位放射線照射装置 −サイバーナイフについてー (2001/08)
Radiosurgery vs Radiotherapy
サイバーナイフ
遺伝子関連
札幌医大が遺伝子治療承認 閉塞性動脈硬化症患者らに (2003/05/19)
遺伝子治療実施を一時中止 白血病の発症で米政府 (2003/03/26)
遺伝子治療で確実な効果 −大阪大学での閉塞性動脈硬化症治療―(2002/05)
血管拡張術後の再狭窄に遺伝子治療 (2001/10)
100歳にとどく長寿遺伝子を発見 (2001/10)
ゲノム研究競争討論会、「民」起点にプロジェクトを
日本におけるゲノム創薬の勢い
末梢動脈硬化性血管疾患の遺伝子治療
再生
再生医療で初の保険適用 関西医大の血管再生に高度先進医療(2003/06/25)
角膜再生 ー大阪大学で幹細胞を利用、臨床試験へ−(2003/03/26)
ヒト神経幹細胞を用いて、サル脊髄損傷を回復 (2002/05)
米国、現存株に限定してヒトES細胞の研究承認 (2001/10)
ドイツで幹細胞注射による心機能の改善に成功 (2001/10)
再生医学の現状と将来
その他
アメリカで痴呆症の新薬を認可し年明けにも市販へ (2003/10/17)
初の完全植え込み型人工心臓患者が151日生存 (2002/05)
60歳女性が無事出産/ 変化するライフスタイルと親子関係のありかた (2001/10)
遺体の神経幹細胞の効果確認/ 札幌医大 (2001/10)
中国で頭部外傷患者に脳の神経幹細胞の自己移植 (2001/08)
胎児の脳細胞移植によるパーキンソン病治療:効果なしと発表
完全埋め込み型の人工心臓 米社が開発、臨床応用へ
トップページに戻る
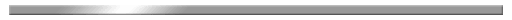
低侵襲医療
日本におけるサイバーナイフ治療、稼動中止(平成14年末)と再開の動き(2004/02/01)
1、経過
平成14年12月財団法人医療機器センターから自主回収(使用停止)の指導があり、これを受け入れて国内のサイバーナイフは稼動を中止、撤去しました。
2、回収理由
米国の製造元は治療精度や安定性の向上のため不断に器機の改良を行い、これが順次日本に輸入されました。平成8年に認可された型式の器機は結果として一台も輸入されず、薬事法違反となりました。
3、健康被害・その他について
全国9施設において今まで2000例をこえる治療が施行されましたが、サイバーナイフに特異的な健康被害は報告されていません。治療費については、既に支払われた医療費を返還することになります。(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/03/h0328-4.html)
4、今後
早期稼動を願う患者さまからの要請やマスコミ報道に後押しされて、次世代のサイバーナイフ(治療時間短縮化とベッドの低床化)が平成15年12月に認可されました。国内の各施設は平成16年度内の治療開始を期待しています。
現在日本国内でサイバーナイフ治療を受けることは出来ませんが、米国、韓国、台湾では治療を行っています。
内容(目次)へもどる
九州大学、国内初の“虚血性心疾患に超音波衝撃波治療” (2003/01/00)
九州大医学部倫理委員会は平成14年12月26日、動脈硬化が原因で起きる狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の患者に対し、体外から衝撃波を当てて心臓に新たな血管をつくりだす治療法の国内初の臨床試験計画を承認した。承認にあたり倫理委は「有効性や安全性の確認が現時点では難しい」として、患者へのインフォームドコンセントをしっかりと行うという条件を付けた。
実施するのは、同大循環器内科の下川宏明助教授らの研究グループ。腎臓結石などの破砕に使われる衝撃波発生装置と同じ原理で、出力が結石破砕の場合に比べて10-15%と低い心臓専用の装置を使う。心臓の超音波エコー画像を見ながら、動脈硬化で血管が狭くなり血液の流れが悪くなっている患部数十カ所にそれぞれ200回ずつ衝撃波を照射、これを一週間に3回繰り返す。
衝撃波の刺激で「血管内皮増殖因子」など、血管をつくる作用のある複数のタンパク質が血管の壁の中で増加、元の血管から枝分かれして患部に血液を供給する新たな血管が形成される仕組みだ。衝撃波は軽い圧迫を感じる程度で痛みはなく、開胸手術と違い繰り返し治療できる利点がある。冠動脈末梢部まで動脈硬化が進み、バイパス手術なども適用外の患者さんには朗報となる。
海外では既に、ドイツなど欧州3カ国で60人に治療を実施。歩くだけで胸痛が起きた重症患者が回復した例もあるという。研究グループがブタで実験したところ、血管造影で新しい血管が確認され、血流が回復し、低下した左心室の運動もほぼ正常化し、不整脈などの副作用もなかった。グループは平成15年1月から、九大病院の入院患者20人を対象に試験を開始する。
内容(目次)へもどる
最新の定位放射線照射装置 -サイバーナイフ- について
まとめ
頭部専用の“ガンマナイフ”、さらに数機種のリネアック装置に続いて、世界的に現在サイバーナイフの導入が進んでいます。脳腫瘍や脳血管奇形、近い将来には肺癌などの体幹部の腫瘍の治療に威力を発揮する本装置の概略を説明します。
1、定位放射線照射とは
病巣を正確に位置決めして(“定位”と言います)放射線ビームを集中照射して壊死させる治療法で、頭部専用の“ガンマナイフ”装置で約
10 年前に開始されました。一回大量照射で治療が終了し、これが外科手術を連想させるため、“手術”や“ナイフ”とよばれました。最近は副作用を減らすための分割照射(この場合には“手術”ではなく“治療”と言います)や、頚部・体幹部病変(肺癌・肝癌・前立腺癌など)への応用が試みられています。優れた放射線科医・外科医・放射線技師からなる治療チームが最新の治療装置を駆使することによって、良好な治療成績が得られるものと考えられています。
2、サイバーナイフの歴史
従来の定位放射線装置の問題点を克服するために、1992 年から米国で開発がはじまりました。1994
年から米国内で臨床応用が開始、日本では 1998年に初めて大阪大学に導入され、現在3施設で稼動中です。
3、サイバーナイフの特徴
1)非侵襲的定位放射線照射装置
米国 NASA開発したミサイル誘導装置を応用した位置監視装置と、それに連動した自動制御ロボットアーム(図1)を採用しています。従来機種では不可欠な局所麻酔による頭部固定が不要となり、画像検査時と放射線照射時に短時間だけマスクを用いるという、老人や小児にも優しい固定方法となりました(図2)。また分割照射が容易になったため、通院治療や、患者さんの都合に合わせた治療スケジュールが組めます。
2)均一な線量分布
6軸自由度を持つロボットアームと特殊な治療計画システムにより、不整形の腫瘍にも均質な放射線の照射が可能となり、従来機種に比較して良好な治療成績が期待できます。
3)高い拡張性
侵襲的頭部固定装置が不必要なため、頭蓋底・頚部・体幹部も治療対象にできます。すでに耳鼻科領域の病巣や頚部腫瘍などで良好な成績をあげています。また近いうちに肺癌・前立腺癌などの治療も開始される見込みです。 (2001/08/01,
http://www.accuray.com/cyberknife.htm)
 図1
図1  図2
図2
内容(目次)へもどる
Radiosurgery vs Radiotherapy サイバーナイフとの関連で 新医療(2000年12月号)
1、 ”radio-surgery”の由来と、今後の動向
”radio-surgery”の名の由来は、細かい放射線ビームを操作して病変部のみを照射する様子が、メスが病変と正常組織との境界を切り裂く様子にたとえたところにあります。最近の動向の第一は、頭蓋内の病変のみを対象としたガンマナイフ装で始まったラジオサージャリーが、機種を新たにして肺癌や肝癌、前立腺癌などの体幹部の病変に対しても応用され始めています。第二の動きとして、”一回大線量照射”から、周囲正常組織の障害を軽減させることを目的としたから”分割照射”へ移りつつあります。
2、定位放射線照射(stereotactic irradiation:STI)の分類
従来の放射線治療とは異なり、病変の位置を局在化(定位化)してそこに放射線を集中させるSTIには、以下の2種があります。(日本放射線腫瘍学会 放射線治療用語集)
定位手術的照射(stereotactic radiosurgery:SRS)
1回照射による定位放射線照射(ラジオサージャリー)
定位放射線治療(stereotactic radiotherapy:SRT)
分割照射による定位放射線照射
3、 定位手術的照射(SRS)の治療対象と適応
本邦ではこの9年間に2万7千人の治療がされました。その内訳は、転移性脳腫瘍(40%)、動静脈奇形(20%)、聴神経鞘腫(10%)、髄膜腫(10%)となっています。最近の3年間では、転移性脳腫瘍の割合が著しく増加しています。
4、定位放射線治療(stereotactic radiotherapy:SRT)への展開
SRSにより、良性疾患(血管性病変や良性腫瘍)を1回大線量照射で消失あるいは制御できれば、
これに勝るものはありません。しかし放射線脳障害のリスクをさけるため、比較大型の病変や重要部分(脳幹、視神経など)に近接する病変などに対して、SRTが勧められる傾向にあります。
コメント
サイバーナイフはラジオサージャリーを目的として2年前から臨床使用が開始された優れた特徴をもつ最新の装置です。しかしラジオサージャリー
(SRS) には10年間の治療経験があります。ラジオサージャリの特集の一部をまとめたので参考にしてください。
サイバーナイフは従来の機器で必要とされる侵襲的頭部固定装置が不要で、独自の病変定位化の機構さらに病変の動きに対応した機構により均等な線量分布と高い精度が保証され、一回照射も分割照射もできるという特徴があります。いっぽう最近では“放射線脳障害のリスクが小さい分割照射を計画するなら、SRS
ほどの高い精度は必要ないため、侵襲的固定装置は不要である”という論調を耳にします。しかしこの意見は分割照射を必要とする根拠と矛盾しますし、侵襲的固定装置が不要であることを強調するがためのような気もします。
頭部専用のSRS機種はガンマナイフ一で00/12/01現在30台(関西では大阪2台、奈良・兵庫・和歌山各1台)稼働中です。サイバーナイフ(稼働中は3台)を除いたSRT機種は5機種で119台(京都3台、大阪11台、兵庫7台、奈良・和歌山各1台)です。
内容(目次)へもどる
サイバーナイフ 第9回日本定位的放射線治療研究会(2000/07)
1.上咽頭腫瘍に対する3次元小容積照射: 北海道大学 放射線科
この7 年間で20病変に追加照射または再照射した。
2.High dose re-irradiation by fractionated stereotactic radiation
therapy for locally recurrent nasopharynx cancer: Samsung Medical Center,Seoul,Korea
x-knife システムで、この4年間、局所再発した17咽頭癌に対して、総線量 54Gy
を一回 2.5-3.0 Gyで分割再照射した。60-70%の局所制御が可能で、再発腫瘍への再照射は有用であった。
3.Micro-multileaf を用いた頭頚部癌の定位放射線治療:大阪成人病センター放射線治療科
この2年間、BrainSCAN with mMLC で、頭頸部癌38症例(上顎癌、上咽頭癌、中咽頭癌)を治療。定位照射単独症例は19例で、他は通常外部照射後のブーストとして定位照射した。一回線量は
2-4 Gy、分割数は5-23回、総投与線量は15-72 Gy 。分割線量は咽頭頭粘膜の急性反応のため
2-4 Gy が限界である。定位照射を局所制御率向上に結びつけるには総線量の増加が必須であり、それには標的をできるだけ小さく正確に限局して設定することがもっとも重要である。
4.頭頚部腫瘍に対するCアームライナックを用いたnon-coplanar3次元conformal照射:東大
放射線科
RSS を用いて、頭頚部悪性腫瘍 11症例(鼻腔悪性黒色腫、副鼻腔癌、嗅神経芽細胞種、涙腺癌など)を治療。5例は初回治療。全例シェルを用いた固定を行い、一回2-3Gy
の通常の分割照射。 照射方向の自由度が増したため、脳幹?脊髄、眼球、視神経といった重要臓器を避けることが容易となり、MLC
を使用してtargetの形をよりconformした線量分布を作ることが可能となった。照射野内の線量の均質性を保つ工夫が必要である。
5.Cyberknifeによる頭頚部領域への定位放射線照射:大阪大学大学院バイオ集学放射線治療学研究部
8症例(上咽頭悪性リンパ腫、C1レベル神経鞘腫、上顎癌、C4レベル悪性黒色腫、多型腺種頭蓋底浸潤、上咽頭癌、口腔癌)。定位放射線照射単独3例(30Gy/3分割/3日)、外照射後のブーストが5例(15Gy/3分割/3日)。8例中7例はPRまたはCRであった。急性、亜急性の有害事象はなかった。
6.頭頚部腫瘍に対するRobotic集光照射:山口大学 放射線科、歯科口腔外科、耳鼻科、小児科・厚南セントヒル病院
Cyberknife を用いて、98-00年の間に、頭頚部腫瘍14症例(初発3例、再発再燃9例、術後予防照射2例)。頭部フレーム(口腔癌の場合は口腔内モールド併用)使用、辺縁線量4-32
Gy。 有効率は86%で、20 Gy 以上の高線量の部位で十分な治療効果が認められた
コメント
Cyberknife は全身を治療対象とする定位放射線治療システムです。このため治療病変部位の視点からは、頭蓋内病変の専用システムであるガンマナイフと競合し、頭蓋外病変も含めた治療(頭頚部、肺など)では他の定位放射線治療システム(RSS,
BrainSCAN、 X-ナイフ、その他)と競合します。頭頚部の治療(サイバーナイフは最近1ー2年の、他の定位放射線システムではここ数年の治療経験)を扱ったシンポジウム
”頭頚部領域等に対する定位放射線照射と3次元 conformal 照射”(6演題)をまとめました。頭頚部病変の病理の種類と関連診療科の多さ、比較的少ない症例数、放射線照射方法の多様さ、各システムの問題点などに着目して下さい。
内容(目次)へもどる
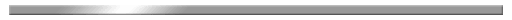
遺伝子関連
札幌医大が遺伝子治療承認 閉塞性動脈硬化症患者らに (2003/05/19)
札幌医科大の遺伝子治療臨床研究審査委員会は03/05/19日、同大の第二外科(安倍十三夫教授)が申請していた閉塞(へいそく)性動脈硬化症とビュルガー病の重症患者への遺伝子治療計画を承認した。23日に厚生労働省に申請、承認が得られ次第、来年初めにも約10人の患者に治療を始める。安倍教授らによると、遺伝子治療は、血管を新しく作る作用のあるヒト血管内皮増殖因子(VEGF)と、血管を太くする作用のあるヒトアンジオポエチン1(Ang1)を、組み合わせ注射する。
閉鎖性動脈硬化症とビュルガー病は、年齢や生活習慣、糖尿病などが原因で、動脈硬化による血流障害を起こす病気。重症患者は足などの患部を切断せざるを得ない場合が多く、切断後も約4割が合併症などで死亡している。
遺伝子治療は、別の遺伝子を使って大阪大(注:国産技術HGF)で行われているほか、VEGF単独での治療も米国タフツ大で行われ、約75%の患者に効果が見られた。しかし、VEGFとAng1を組み合わせての治療は例がないという。
内容(目次)へもどる
遺伝子治療実施を一時中止 白血病の発症で米政府 (2003/03/26)
先天性免疫疾患の遺伝子治療で、治療に用いたベクター(遺伝子の運び役)が引き金とみられる白血病が、フランスで2例確認された。これをうけて米食品医薬品局(FDA)は米国内で同タイプのベクターを使った約30件の遺伝子治療を一時中止すると発表した。
中止対象となるのは、レトロウイルスと呼ばれるウイルスから作られたベクターを用いた遺伝子治療。X連鎖重症複合免疫不全症という重い先天性免疫疾患を対象に行われていた遺伝子治療で、マウスに白血病を起こすレトロウイルスから作ったベクターが使われていたが、この治療法が開発されたフランスで患者二人が白血病を発症していたことが判明。ベクター投与でがん遺伝子が働きだした可能性が高いことが分かった。
FDAは昨年、最初の白血病の発症が報告された直後に、同じ病気を対象にした治療3件の実施を見合わせていた。今回FDAは「米国内での発生例はないが、治療の危険度を見極める必要がある」として、対象をレトロウイルスを使って造血幹細胞に遺伝子を導入するタイプの遺伝子治療に拡大した。
コメント
遺伝子治療では、侵襲が小さく限られた回数の治療で、タイムリーに目的とした蛋白質や細胞が適量産生されて、長期的に充分な効果が得られる必要があります。このように、“タイムリー・適量・長期” などは遺伝子治療のキーワードで、これが欠ければ無効あるいはガン化に直結します。遺伝子治療の初期段階は安全性の確認に尽きるようです。(遺伝子治療一般のコメントで、この記事にはアウトオブフォーカスかも知れません。)
内容(目次)へもどる
遺伝子治療で確実な効果 −大阪大学での閉塞性動脈硬化症治療― (2002/05)
慢性疾患としては日本初の遺伝子治療が「慢性閉塞性動脈硬化症」を対象に大阪大学で実施され、確実な効果を確認、次のステップに進むことになりました。患者さんは6人で40-60代、これまでの治療では効果が見られなかった重症者で、下肢の血管がふさがり、痛み、潰瘍・壊死を伴っていました。3人が慢性閉塞性動脈硬化症、3人が自己免疫病の閉塞性血栓血管炎でした。平成13年6月から荻原俊男教授(老年医学)のチームによって、血管を新生させる作用を持つ肝細胞増殖因子(HGF)の遺伝子を、ふくらはぎなどの筋肉に注射、1カ月後に2回目の注射を行いました。昨年暮れに総合評価が行われ、6人中5人は痛みが和らぎ、3人は歩けるようになりました。回復した5人では、注射した部位で血管の増生が確認され、足の血圧や潰瘍の縮小が認められました。副作用・安全性にも問題ありませんでした。(大阪大医学部遺伝子治療学のインターネットホームページ「遺伝子治療と臨床研究」参照)。
コメント
遺伝子治療や再生医療が急速な勢いで試みられています。なかでも血管増殖因子(あるいはこれを産生する遺伝子)・血管を新生する(骨髄)幹細胞などで血流の低下を改善する試みは、対象となる患者さんが多いこと(心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症など)、作用物質の投与方法が比較的簡便で普遍性があること、種々の投与経路が工夫できること、などの特徴をもっています。脳神経外科領域でも脳梗塞・もやもや病などへの応用、血行再建術との成績比較、などが新しい検討課題になると予想されます。
内容(目次)へもどる
大阪大学、再狭窄の防止に人工遺伝子治療を承認 (2001/10)
大阪大医学部の倫理委員会は8月9日、加齢医学講座(荻原俊男教授)が申請した動脈硬化病変に対する血管拡張術後の再狭窄を防ぐ人工遺伝子「デコイ」治療の実施を、腸骨動脈や冠動脈の閉塞性動脈硬化症の十二人を対象に承認した。再狭窄は血管拡張後の炎症反応によるもので、NFκBというタンパク質が遺伝子の特定部分に結合し多様な催炎因子を活性化させるためと考えられている。NFκBにデコイを結合させ遺伝子への結合を阻害すれば、炎症を抑える効果が期待できるという。
コメント
同教授は本年3月から「HGF遺伝子プラスミドを用いた末梢性血管疾患(慢性閉塞性動脈硬化症・ビュルガー病)の治療のための遺伝子治療臨床研究」を開始し、将来下肢の切断が予想される患者に血管新生因子(HGF)の筋肉内注射を行っています。
内容(目次)へもどる
100歳にとどく長寿遺伝子 米チームが存在発見 (2001/10)
発表チームは前回の調査で、兄や姉が100歳以上の人は、身内に長寿者がいない人に比べ91歳以上の長生きができる可能性が4倍高く、長寿には遺伝的要因が大きいと指摘していた。今回98歳から109歳の長寿者137人を選び出し、長寿者の弟や妹で91歳以上の人を含めた合計308人のゲノムを分析、共通点を探った。その結果4番染色体に100歳にとどく長寿を可能にする遺伝子があることを、8月28日付の米科学アカデミー紀要に発表した。長寿遺伝子はひとつか、複数の場合でも数個とみられる。同チームはこれらの遺伝子は老化の進行を遅らせる働きがあるとみている。線虫やショウジョウバエなど下等な生物では長寿遺伝子が見つかっていたが、人での発見は初めて。
内容(目次)へもどる
ゲノム研究競争討論会、「民」起点にプロジェクトを
(日本経済新聞・第2部 6 - 7 面のサマリーです(2000/11/17)
1、基調講演
ヒトゲノム(人間の全遺伝情報)は既に99%解読されており、クリントンは「人類がこれまで作った最も重要で最も驚くべき地図だ」と述べた。
遺伝子解明を産業という視点で見ると、通産省の試算では2000年に1兆円、2010年には25兆円の関連市場が生まれるという。遺伝子の解読技術や分析ノウハウ、情報技術(IT)と結びついたビジネスが見込める。医療品や遺伝子治療のほか、今までにない診断法も出てくるだろう。食品分や環境分野も関連産業として成長が期待できる。 (藤野雅彦 武田薬品工業会長)
2、「遺伝子の世紀 ヒトゲノム解読の衝撃を越えて」 研究の現状と成果
(米国セレーラ・ジェノミクス社がゲノム解読の官民レースに勝ったことを受けて)ポストゲノムとの言葉にはゲノム研究が終わったという響きがあるが、現状はまだ遺伝子の配列を読み終えただけ。例えばエジプトの遺跡で発見した碑文の破片を全部つなぎあわせることはできたのだが、何が書いてあるかは分からない、という状況にある(宮田満、日経)。(宝酒造がゲノム解読センターを立ち上げたことを受けて)よく「今ごろゲノム解読を手がけても遅いのではないか」と言われるが、様々な動植物や微生物などのゲノム解読は今後の産業応用の視点からも不可欠なテーマであり、これからが本番だ。遺伝子を効率的に検出するDNA(デオキシリボ核酸)チップを使ったがんの悪性度分析にも力を入れている(加藤郁之進、宝酒造副社長)。
(武田製薬がセレーラ・ジェノミクス社からデータ提供を受ける契約をしたことを受けて)米国製の「辞書」を買ったという意味であって、よい辞書があれば自動的によい文章が書けるわけではない。ゲノム研究で日本は欧米に敗れ去った、との評価をよく耳にするが、何か誤解しているのではないか(藤野雅彦)。
3、「21世紀への課題」
ポストゲノム研究には三つの流れがある。一つはヒトだけでなく、チンパンジー、マウス、植物など多様な生物の遺伝情報を解読すること。二つ目は遺伝子がゲノム上のどこにあって、どのような機能を持つかを解明すること。第三の方向はヒトの多様性の分析だ。こうした分析から、テーラーメード医療や新しい健康産業が誕生するのではないか(
宮田満)。
(テーラーメード医療に関連して)遺伝子を全部調べることができたら、病気の診断の面で非常に大きな威力を発揮するだろう。遺伝病は100%遺伝子に起因する病気だが、肥満で約80%、アルツハイマーで約50%、糖尿病で約40%の割合で遺伝子に関係することが分かってきた。各疾患の原因遺伝子が特定されていけば、個人によってどんな病気にかかりやすい体質かが分かり、予防につながる(藤野雅彦)。
(新しい健康産業に関連して)「人間」をデーターベース化できる可能性が出てきた。例えば20-30年もすれば、赤ん坊の全遺伝情報が入ったプラチナカードを出生祝いの贈るのが当たり前になるかもしれない。そのデータに沿って、最もアレルギーが少ない肌着のダイレクトメールが送られてくる。そのうちこの分野の才能があるからといっていろんな塾の話しが来たり(教育面への影響の示唆か?)、結婚式の案内が来たり(家族の在り方や子孫?)して、最後に葬儀場からの広告(病気や寿命?)が届く(
宮田満)。
コメント
日本のゲノム研究は、世界から遅れている、もう追いつけないとも言われていますが、産学のリーダー(の一部?)がまだ活躍の余地ありと判断し、今後の展開を討論しています。
内容(目次)へもどる
日本におけるゲノム創薬の勢い (日経01年02月20日)
本年2月にヒトゲノム(人間の全遺伝情報)の配列データーが公表され、ゲノム創薬の新段階としてゲノムが作り出すたんぱく質の解明(構造と機能)が加速してきた。病気の原因になるたんぱく質を同定してその制御方法を見つければ、根本的な治療につながる。またたんぱく質そのものを医薬品として使用できる可能性もある。
病気に関与するとみられる三千から五千のたんぱく質の機能はほとんど未解明で、ゲノム解読で米企業に出遅れた日本企業にも巻き返す余地がある。しかし、この中でいかに有用なたんぱく質を手にするかが重要で、それゆえ研究のスピードを速める戦略が必要になる。
武田薬品工業、三共、山之内製薬など国内の大手製薬企業20社以上が参加する「たんぱく質構造解析コンソーシアム」(仮称)では、高輝度光科学研究センター(兵庫県)の大型放射光施設「SPring−8」の強力な光源を利用して、通常のエックス線解析では困難なたんぱく質の立体構造を解析する。また、他社に先駆けてたんぱく質の機能を特定することが将来の生き残りのカギになるとみて、以下の提携が続いている。
第―製薬は富士通など(VBとたんぱく質情報利用の新薬開発)、持田製薬は理化学研究所、三菱化学はウェルファイドと協和発酵(遺伝子・たんぱく質研究の新会社ジェンコムを設立)、富士レビオは米VB(たんぱく質チップ開発)、宝酒造は米ジーンフォーマティックス(カルフォルニア州)(たんぱく質機能解析受託)、日立製作所はたんぱく質機能解析の米ミリヤッド・ジェネティックス(ユタ州)(解析受託)、島津製作所は豪プロテオーム・システムズ(たんぱく質解析装置開発)
内容(目次)へもどる
末梢動脈硬化性血管疾患の遺伝子治療 (2001/03)
厚生科学審議会科学技術部会は3月19日、阪大の荻原俊男教授が申請していた「HGF遺伝子プラスミドを用いた末梢性血管疾患(慢性閉塞性動脈硬化症・ビュルガー病)の治療のための遺伝子治療臨床研究」を承認した。これまで遺伝子治療は癌や遺伝性疾患などが対象だったが、慢性疾患に対する承認は今回が初めて。今回の臨床研究では、将来下肢の切断が予想される患者に血管新生因子(HGF)の筋肉内注射を行う。
既に米国では同じ血管新生作用があるVEGF遺伝子 (vascular endothelial
growth factor)を使った治療が行われ、200人以上の患者の治療が終了している。HGFを用いる臨床研究は世界で初めてで、HGFはVEGFと同等以上の血管新生作用があると言われている。
阪大遺伝子治療の承認保留 米国の情報で厚労省など
米国立がん研究所の実験で、HGF遺伝子を入れたマウスと、がん抑制遺伝子を欠損したマウスを交配すると、生まれたマウスに高頻度で横紋筋肉腫(にくしゅ)という珍しいがんが発生するという結果が出た。これを受けて厚生労働省は二十九日、「安全性にかかわる新しい科学的情報が米国からもたらされた」として、専門家による検討結果が出るまでの間、大臣による正式な承認を保留すると発表した。
コメント
遺伝子治療は遺伝子欠損疾患や悪性腫瘍が対象と考えられてきました。しかし患者数が多く、また投与方法が比較的容易な動脈硬化性病変に対してこの種の治療が試みられ、大きな波及効果が期待されます。脳外科領域でも、虚血性疾患やモヤモヤ病など、対象になると思われます。しかし新しい治療故に未知の副作用の可能性も指摘されています。
内容(目次)へもどる
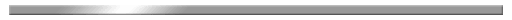
再生
再生医療で初の保険適用 関西医大の血管再生に高度先進医療(2003/06/25 朝日新聞)
中央社会保険医療協議会が、関西医大病院(大阪府守口市)など3病院が実施する骨髄の幹細胞を移植することによる血管再生、その他2つの治療に対して、平成15年7月1日から高度先進医療を適用することを決めた。費用のうち投薬費や検査費が医療保険の対象となる。再生医療では、初めての保険適用となる。
保険適用となる再生医療は、手足の細かい動脈が詰まって血流が悪くなる閉塞性動脈硬化症とバージャー病で、患者自身の骨髄液を濃縮して閉塞動脈の周囲に注射し、新しい血管ができるのを促す治療法。関西医科大病院の他に、久留米大病院(福岡県久留米市)、自治医科大病院(栃木県南河内町)の3病院が対象となる。
治療費は百数十万円かかり、個人負担が原則だが、これまでは病院が研究費で肩代わりしてきた。高度先進医療が適用されたことで自己負担は30万―50万円に軽減されるという。
内容(目次)へもどる
角膜再生 ー大阪大学眼科が幹細胞を利用し、近く臨床試験へ− (2003/03/26)
目の角膜などから細胞を取り出して培養、シート状の角膜上皮を再生し、目に張り付けて角膜の損傷を治療する臨床試験を、西田幸二大阪大講師(眼科学)らの研究グループが来月から実施する。
研究グループは岡野光夫東京女子医大教授と共同で、ウサギの角膜上皮や口の粘膜から多様な組織に分化、成長する能力がある幹細胞を採取、シャーレ中で厚さ0.05ミリの薄いシートに再生させることに成功。シートは透明度が高く、角膜上皮として機能することを確かめている。
手術後の定着を考慮すると、幹細胞の採取は口内の粘膜からよりも角膜からの方が望ましいという。
西田講師は「片目の角膜が損傷しているなら、もう片方の角膜から、両目の角膜の損傷なら、粘膜から幹細胞を採取するようにしたい」としている。角膜損傷は物が当たって傷ついたり、薬剤が目に入るなど外的要因のほかに、感染症などでも起きる。
内容(目次)へもどる
ヒト神経幹細胞を用いて、サル脊髄損傷を回復 (2002/05)
ヒト神経幹細胞を用いてサル脊髄損傷を回復させることに慶応大医学部(岡野栄之生理学教授)らのグループが世界で初めて成功した(01/12/10)。実験は、ヒトの神経のもとになる「神経幹細胞」を胎児の脊髄から分離し大量に増殖させた。これを、脊髄を損傷して両手の動きが不自由になった小型の猿5匹(いずれも成獣)の脊髄に移植した。その結果、10% 以下にまで低下していた筋力が、8週間後には正常時の半分近くにまで回復した。移植した幹細胞が神経細胞に成長し、切れていた神経の回路が再びつながったと考えられるという。
ヒト胎児から神経幹細胞を効率よく分離・増殖させる技術の開発、移植時期の選択が良好な結果になったという。霊長類の猿での治療効果が確認できたことで、ヒトの脊髄損傷を治療できる可能性が示された。今後は、ヒト胎児の取り扱いの社会的合意、脊髄損傷から時間のたった慢性期に有効な治療法の検討が課題となる。
内容(目次)へもどる
米国、現存の約60株に限定してヒトES細胞の研究予算承認 (2001/10)
ブッシュ米大統領は8月9日、現存する約60のヒトの胚性幹細胞(ES細胞)の研究に限定して「今年は二億五千万ドルの連邦政府予算の支出を認める」と述べた。
2004年の再選戦略にも大きく影響する問題だけに、就任以来最も厳しい政治決断だったようだ。
先端医療、科学技術の分野で「超大国」の米国でES細胞研究の是非についてここまで論争が盛り上がった背景には、キリスト教に基づく倫理観を重視する政治勢力「宗教右派」が米国社会に影響力を持っているという事実がある。同派の組織票によってきわどい大統領選を勝ち抜いたブッシュ大統領は選挙戦当時反対を表明していたこともあり、心情的にはES細胞研究にゴーサインを出すのをためらっていたとされる。
しかし、米国が進出しなければ再生医療の分野で欧州諸国や日本に先を越され、医薬品業界に莫大(ばくだい)な利益をもたらす機会を逃す恐れがある。ブッシュ政権は結局、この分野の研究・開発でも優位を確保することが「国益」と判断したといえる。(01/08/09)
内容(目次)へもどる
独大学が世界で初めて、幹細胞注射で心機能の改善に成功 (2001/10)
ドイツのデュッセルドルフ大医学部は8月 24 日、同大付属病院のシュトラウアー教授(心臓外科)を中心とするチームが心筋梗塞(こうそく)の患者に患者自身の骨髄から取った幹細胞を心臓の動脈に注射し、10週間後には心筋の壊死部分が1/3
に縮小、心機能が「明らかに改善」したと発表した。だが、幹細胞が心筋細胞に変わったのか、心筋細胞の再生を助けただけなのかは不明としている。同病院では三月以降、この男性患者のほか38歳から67歳の患者計五人にも同じ治療を施し、経過はいずれも順調だという。シュトラウアー教授は「移植以外に方法がない重症患者の治療に新たな可能性が生まれた」としている。
骨髄幹細胞注射による心臓の修復は今年4月、米国の研究グループがマウスで注入し、1週間から11日で増え始め、心筋細胞や血管の細胞に変化して傷んだ組織を修復したとしている。 今回の治療では、倫理的な問題もあるヒト胚性幹細胞ではない点が注目される。
内容(目次)へもどる
再生医学の現状と将来 Physicians' therapy manual Vol 11 13(5),2000(著:高久史麿)
1、ES細胞を用いた細胞移植
再生医学は1998年に発表されたヒトの胚性幹細胞(embryonic stem cell;ES細胞)の開発に端を発した分野で、ES細胞から各系列に分化した前駆細胞を用いる細胞移植が医療の各分野で行われると予想される。この中で特に注目されるのが神経細胞である。既にParkinson病に対してヒトや豚の胎児の脳細胞の移植が諸外国で行われているが、ES細胞から神経細胞への分化に成功すれば、その神経前駆細胞がParkinson病、Alzheimer病等の治療に広く用いられる可能性がある。またマウスの糖尿病モデルで示されたように、ヒトのES細胞由来の膵島細胞の移植が将来の方向として当然考えられる。
2、胚性幹細胞でない幹細胞の応用、自己の幹細胞の使用
しかしヒトの胚細胞の利用に対する倫理的反対、患者とES細胞との間の抗原性の問題などがある。これに対して患者自身の幹細胞を応用する方法が試みられている。
骨髄中の基質には、骨髄移植に用いられる血液細胞の幹細胞とは別に間葉系幹細胞(mesenchymal
stem cell ; MSC)が存在し、骨、軟骨、脂肪細胞、筋肉、心筋、肝臓、神経等の細胞にも分化し得ることがわかった。その中でも神経細胞への分化がヒトでも証明され、将来の神経疾患への応用が注目される1)。また脳中にも様々な細胞に分化し得る幹細胞が存在することがマウスで証明されており、我々の体の中には思いもつかないような部位に多能性の幹細胞が存在している可能性がある。例えばヒトの角膜の辺縁部の一部を取り移植したところ角膜の再生に成功したという報告2)などは、片方の角膜にのみ障害がある場合の角膜再生に利用できる可能性が示唆される。また最近、膵島の幹細胞がヒトにも同じように膵管上皮細胞中に存在することが報告されており3)将来、膵島幹細胞の移植を重症の糖尿病の治療も期待される。
1)Woodbury,D.,Schwarz,E.J.,Prockop:J.Neurosci.Res.561:364-370,2000.
2)Tsai:N.Engl.J.Med. 343:86-93,2000.
3)Bonner-Weir,S.:Proc.Natl.Acad.Sci.USA
97:7999-8004,2000.
コメント
臨床医として近い将来に実現する最新医療のイメージを把握しておく一助になればとまとめました。
内容(目次)へもどる
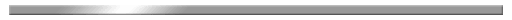
その他
アメリカで痴呆症の新薬を認可し年明けにも市販へ
(2003/10/17)
米食品医薬品局(FDA)は平成15年10月17日、症状が比較的進んだ中等度から高度のアルツハイマー型痴ほう症の治療薬、塩酸メマンチン(一般名)を認可した。FDAによると、これまでに認可した薬はすべて初等から中等度の患者向けで、症状が進んだ患者向けの薬は初めてとなる。メマンチンは既に欧州で認可され、日本でも臨床試験中。米国内では来年早々にも、薬局で市販される予定だが、認可前から注目され、インターネットを通じて入手する患者が増えていた。FDAによると、メマンチンはアルツハイマー型痴ほう症の発症に関与している脳内の情報伝達物質の働きを抑制。神経細胞を保護して、痴ほうの症状の進行を遅くする作用がある。米国内の計650人を対象とした臨床試験などの結果、この薬を服用している患者では、記憶力や自力でトイレに行くなどの日常生活能力の衰えが目立って抑えられることが確認された。
内容(目次)へもどる
初の完全植え込み型人工心臓患者が151日生存 (2002/05)
世界初の完全埋め込み型人工心臓の装着手術を受けた米国人(59歳男性)が01/07/02の手術から151日目の01/11/30、手術を受けた米ルイビル大学(ケンタッキー州)で死亡した。11月11日に血栓が原因とみられる脳卒中を起こし、29日腹腔内に出血し多臓器不全に陥り死亡したもので、人工心臓そのものの不調などが原因ではないという。
手術前には心臓病、糖尿病、腎不全を併発して寝たきりで余命約1カ月と診断されていた。一時は外食や釣りができるまで回復、医師団は「患者の生活の質の向上に大きく貢献した」と強調し、米医学界も余命を5倍にしたことは評価できるとしている。
人工心臓は米医療機器会社アビオメドが開発したもので、ソフトボール程度の大きさで重さは約1キロ、チタン製ポンプに血管に相当する四本のチューブが付いた構造。外部電池の電力を体外のコイルから皮膚越しに体内のコイルに伝え、内部の電池に充電しながらポンプを動かす仕組み。電源コードやチューブ類が体外に出ないため患者の生活範囲が飛躍的に向上する。装置の寿命についてはよく分かっておらず、装着当初、医師団は「余命を2倍に伸ばすことが目的」としていた。米国ではトゥールズさん以降、5人の患者が同タイプの人工心臓の装着手術を受けている。
コメント
このニュースのタイトルは“151日で死亡”でしたが、ここでは“151日生存”に改めました。151日は決して充分長くはありませんが、有意な生活の機会を与えた、また故障を許されない生体内埋め込み式の人工臓器であることを考えて、かなりの成績を残したと評価したいと思います。
内容(目次)へもどる
60歳女性が無事出産/ 変化するライフスタイルと親子関係のありかた (2001/10)
慈恵医大病院で七月下旬、六十歳の日本人女性が、米国で卵子の提供を受け、夫の精子による体外受精で妊娠、帝王切開で出産(初産)した。国内では最高齢の出産とみられる。この女性は50代半で結婚し、夫婦の子供を望んだが「高齢なので国内で認められている方法では妊娠は無理」とされた。57歳の時にネバダ州の不妊治療施設で、「妊娠・出産に耐えられる健康状態だ」と判断され、若い東洋人女性から提供された卵子を夫の精子と体外受精させ、子宮に移植した。2回目の移植後に妊娠が判明した。米国での医療費用は計600万円近くで、また世界最高齢の出産記録は63歳。
7年ほど前から同センターを通じて出産した閉経後の女性は計43人。56歳での出産が2例、54歳で双子を産んだ人もいる。いずれも帝王切開で出産した。国内で不妊治療を続けているうちに年齢を重ね、閉経に至った人が多いが、ライフスタイルに合わせ、高齢での出産を意識的に選択するケースも出てきた。キャリア志向や晩婚化で出産年齢が高くなる中、50代以降での出産を希望する女性はさらに増えそうです。年齢が進むほど卵子が老化して妊娠しにくくなるが、子宮はホルモン剤で妊娠に適した状態に整えられるため、若い女性から卵子提供を受ければ閉経した女性でも妊娠が可能になった。国内ではできないとの理由で、海外渡航による実施例が増加する現状に論議がわいている。
コメント
ライフスタイルの変化が従来の親子関係の在り方に波紋を投げているようです。米国では40-44
歳の出産がこの5年間で 25%増加したそうですし、親権(母権)の定義 ―DNA、身ごもった女性、育てる人など― も複雑化しつつあります。日本の医療を担う側は難しい対応を迫まれているようです。またこのような中で育つ次の世代の人たちは、どのような家族観をもつのでしょうか。
内容(目次)へもどる
遺体の神経幹細胞を培養 動物に移植し効果を確認(2001/10)
札幌医科大(札幌市)は8月8日、解剖学習のために献体された遺体の脳から多様な神経細胞の基となる神経幹細胞を分離・培養し、それを動物に移植したところ修復効果が得られたと発表した。がんや老衰で死亡した70−90歳代の7人から、死後10時間以内に脳の側脳室と呼ばれる部分の神経幹細胞を分離・培養し、脳梗塞や脊髄損傷を起こしたマウス、脊髄損傷のサルに移植した。その結果、神経組織の修復や機能改善の効果が確認できたという。脳梗塞(こうそく)やパーキンソン病など、傷んだ神経の再生医療に広く応用可能な研究成果として注目されそうだ。(01/08/08)
コメント
再生不可能とされた中枢神経系の再生医療の方法として注目されています。1月前に中国でも頭部外傷症例への自己移植が報告されました。自己移植での効果確認、他家移植時の免疫の問題が課題とされています。
内容(目次)へもどる
脳の神経幹細胞の自己移植を頭部外傷患者に応用、中国発表(Aug.01)
6月18日、上海の復旦大学付属華山病院で、患者自身の脳の神経幹細胞を移植する手術に成功したと報じた。この女性は四十歳で、今年4月長さ約10センチの鋭利な物が刺さり脳に損傷を受けた。付着していた脳の神経幹細胞を分離、培養し、約五百万個の神経幹細胞を注射で脳に移植したという。女性は当初、自分がどこにいるか分からず肉親の判別もできなかったが、手術後に症状は改善、針に糸を通すような動作もできるようになったという。神経幹細胞は脳細胞などの基になる細胞で、パーキンソン病などで傷んだ神経の再生医療に役立つと期待されている。しかし、幹細胞の移植による記憶や認知などの複雑な脳機能の回復は、まだ技術的に困難と考えられており、日本国内の専門家の間には今回の発表に懐疑的な見方もある。
内容(目次)へもどる
胎児の脳細胞移植によるパーキンソン病治療:効果なしと発表
New Eng J Med 要約 (医師会インターネットデイリーニュースから(2001/03))
80年代から難治性パーキンソン病の患者に行われてきた胎児の脳細胞の移植は、治療効果がないことが発表された。試験ではパーキンソン病の患者40人を対象に半数に脳細胞移植を実施、残る半数には細胞を移植しない偽の手術を行った。その結果、61歳以上の患者では、移植を受けた人と偽手術を受けた人で病状に差は出なかった。60歳以下で移植を受けた人は治療薬を飲まない状態では、偽手術を受けた人に比べ動作に改善が見られた。しかし、通常のパーキンソン病患者が服用する薬を飲んだ状態では差がなかった。このため、手術よりも薬の方が改善効果があると考えられた。さらに移植を受けた患者のうち5人に、分泌する神経伝達物質が多すぎるのが原因とみられ運動障害が発生した。
コメント
最も高いエビデンスとされる prospective randomized controlled study の結果です。ヒトへの偽手術を諾とする米国のモラル、本治療法に長年取り組んできた研究者の努力、種々の思いを込めたエビデンスです。
内容(目次)へもどる
完全埋め込み型の人工心臓 米社が開発、臨床応用へ
(医師会インターネットデイリーニュースから(2001/03)
米医療機器会社「アビオメド社」(マサチューセッツ州)が十八日、チューブ類が体外に出ない完全埋め込み型の人工心臓を開発し、近く五人の重症心臓病患者を対象に臨床試験を始める、と発表した。 チタン製のポンプに、実際の心臓のように四本のチューブが付いた構造で、重さ約1.4キロ。本体を手術で体内に埋め込み、皮膚をはさんで二つのコイルを設置。外部の電池でつくった電力を体の外側のコイルから皮膚ごしに体の内側のコイルに伝える仕組みで、チューブや電線はなく、このタイプは世界で初という。運動をした時などにはセンサーが働いてポンプの動きが速くなるので、現在は日常生活を送れない患者も、歩き回ることができるようになる。同社は「(人工心臓の)寿命は六カ月程度だが、患者の生活の質は大きく向上するはずだ」としている。
内容(目次)へもどる
トップページへもどる
 図1
図1  図2
図2