�@��Ìo�ρE����
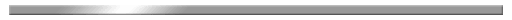
���e
����҈�Â̗}���ւ̓����@�@�i2003/08/27�j
�č��ň�Ñi�}���A���z�����ň�t�̔p�ƁE�]���������@�i2003/11/02�j
�č��̑�ֈ�Â̍��܂�@�@�|�I�A�w���A�����A�A���Ɍ��\�@�i2003/08/14�j
��p�{�݊�̍������s�\���@�@���㋦�E�Z�p�]�����ȉ�� �@�i2003/11/17�j
������9��w����w�E���w�a�@���A6��w�͕a�@�����u��C���v�i2003/10/03�j
�㔭��̉��i������Ɉ����@�u�V��̂W���v�������ց@�i2003/11/28�j
��Ƃɂ��Ă̘b��
�@ �@�P�A��Ɛi�� �@�i2003/10/08�j
�@�@�Q�A��Ƃ̕]���@�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�������@�@�i2003/06/01�j
�@�@�R�A���ܖ�ǂƂ̘A�g�̓���@�i2003/06/01�j
���@��Â̕�]����15�{�݂ɔ����@�i2003/04/03�j
����v�����F�@�i2003/03/12�j�@
�@�@�@�@�P�A�u���R�f�Áv�Ɓu���x��i��Áv�Ɍ����Ċ�����ЎQ��OK�@
�@�@�@�@�Q�A�O���l��t�̎���ɘa
���ی��� 10% �l�グ���� 3200 �~�ɁA�n��Ԋi���͊g��@(2002/09/18)
�a�@�I�с@�Ǘᐔ���p�����Ȃǂ�ڈ����@�@(2002/05)
�p���A����ŊC�O�Ŏ�p���@�|��Î����s�������O�ʼn����[�@(2002/05)
e�w���X�@���{�ł��g��̋@�^�@�@�\���ҁE��t�̊W���ω��A�V�����ۑ���[
�@(2002/05)
��ȑ�w���w�a�@�A�����ց@(2002/05)
��Ñ҂����Ȃ��̉��v�@�P��ځ@���傷���Ô���ǂ��}���邩�@(2001/10)
��Ñ҂����Ȃ��̉��v�@�Q��ځ@��Ô��N���ǂ����S����̂��@(2001/10)
�×{�^�a���Q�̐����x��A��Õی��ɂ��Љ�I���@�͉������ꂸ�@(2001/08)
�ݑ��Â͍��Ȃ��K�v��
�Y�ƂƂ��Ă̈��
���ی��P�N�A���p�L�т�
�����a�@�E�×{���@�T�N�ԂłR�Q�{�݂��팸
���I�a�@�̖�����
�}�������@��Âɂ�����DRG�^PPS�̖��_
����̐S���ڐA���ی��K��
�����Ȉ��
�����K���a�̗\�h�ɓw�߂�z�K�����a�@
�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
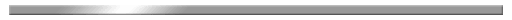
����҈�Â̗}���ւ̓����@�@�i2003/08/27�j
�P�A���{������҂ւ̈�Ô���p�~��
�@���{�͕���15�N8��27���V�l��Ô�����ꕔ�p�~����ȂǕ{�Ǝ��Ŏ��{���Ă����Ô�̏��������������j���ł߂��B��Ô�S���������グ�����̈�Ð��x���v�ŁA�{�̏����z����������������������Ɗ낮�����B�{�ɂ��ƁA�N����200���~�ȉ��̎s�������Ŕ�ېŐ��т�65-69�̍���҂́A���̐��x�ł͈�Ô��3�����S�����A�{�̏�����1�����S�ł���ł���B�{�̈�Ô���z�͖�320���~�i2003�N�x�\�Z�j�ŁA03�N�x�̑Ώێ҂�14.4���l�B4���̈�Ð��x���v�⏭�q����Љ�̐i�s�ŕ{�̕��S���c��ނƔ��f�A�����p�~�����߂��B
�@�܂��A�{�͑S�z�����������Q�҂̏�����1000���~����500���~�O��ɐ�������B�S�z�����̕�q�ƒ����c���ɂ͌��z1000�~�܂ł̖{�l���S�����߂�B����ŁA���c����Â̏����Ώ۔N���2�Ζ�������3�Ζ����ɍL����ق��A���q�ƒ�������̑Ώۂɉ�����B
�@��Ô�����߂����Ă͍�N�ɂ��������Ă����サ�����A�m���^�}�̌����}�Ȃǂ̔��Ő摗�肳�ꂽ�o�܂�����B���N2���̒m���I�o�n�̈ӌ����ł߂Ă��鑾�c�[�]�m���ɂƂ��ẮA9���̒��{�c��Ō������Ή�������ꂻ�����B
�Q�A����҈�Ô�}���Ŏw�j�@�����̂��ƂɗL���҉�c��
�@�����J���Ȃ͕���15�N8��26���A����҈�Ô��}�����邽�߂̏d�_�ۑ��ݒ肵�A���̎��g�݂�]������L���҂�������o�[�Ƃ���g�D�������̂��Ƃɐݒu����悤���߂�w�j���܂Ƃ߂��B����͌��J����28���ɂ���������B
�@70�Έȏ�̍���҈�Ô�͔N�Ԗ�12���~�ƈ�Ô�S�̂�4���߂����߂Ă���A�n��ň�l�������Ô�Ɋi��������̂�����B���̂��ߎs�������x���ō���҈�Ô�̎��Ԃ�c�����A����������Ĉ�Ô�S�̗̂}����}��̂��_�����B
�@�w�j�́A�s���������@�E�O���ʂ⎾�a�ʂɍ���҂̈�l�������Ô���f�����Ȃǂ��Z�o�A�s���{�����f�[�^���W�A�S�����ςȂǂƑΔ䂵�ĕ��͂���Ƃ��Ă���B��̓I�ɂ́A���ׂĂ̓s���{���ƍ���҈�Ô�̐L�т������s�������A�w���o���҂��ÊW�ҁA��Õی����^�c���Ă���ی��҂₻�̉����ҁA�s�����S���҂Ȃǂō\������g�D��ݒu�B�n��̓����܂����v������肷��悤���߂��B����Ɍ��J�Ȃ͓s���{���ɑ��A�f�Õ�V�����i���Z�v�g�j�Ɋ�Â����ڍׂȕ��͂��w��������j���B
�@���{�A�^�}�̓T�����[�}����̈�Ô�ȕ��S��2003�N�x����3���Ɉ����グ�邱�Ƃ����肵���ہA��Ô�S�̂��グ���Ă��鍂��҈�Ô��}������w�j�̍�������߂Ă����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�č�19�B�ň�Ñi�}���A���z�����ň�t�̔p�ƁE�]���������@�i���o2003/11/02�j
�@�ē암�~�V�V�b�s�B�̔_���ō��t�A�ߌ����N�����B��҂��o�C�N���̂œ����ɏd�������B�~�}�����͉Ƒ��ɍ������B�u��ԋ߂��a�@�܂œԂ�����܂��v�B��N�B��̐_�o�O�Ȉオ��������A�B�s�܂Ŕ������Ȃ���Ύ�p�͕s�\���Ƃ����B���T�Ԍ��҂͑�������������B�B�S�̂ł��̓�N�ԁA�_�o�O�Ȉオ41�l����27�l�Ɍ����A��@�����点�Ă������ł̎��̂������B�u�ނ͗���������Î��̍ٔ��̋]���҂��B�v
�@��Î��̂ŁA���_�I��ɂȂǔ�o�ϓI����50���j�i��5��500���~�j�ȉ��̔�����������߂Ă���̂�12�B�B����̂Ȃ��B�ł͈�ÊW�ґ��ɍ��z�Ȕ������𖽂���]�����������A���ϔ����z��1994�N��110���j����390���j�ɒB�����B���̂��߈�t���x�������̕ی��̊|����������2�A3�N�ʼn��{�ɂ����ˏオ���펖�ԂƂȂ��Ă���B�u�_�C�G�b�g�̖������ŋ����ꂵ���Ȃ����B�v97�N�A����5�l�̑i���ɑ��A���B�W�F�t�@�[�\���S�̔��R�������Ђ�1��5�疜�j�̔����𖽂����̂����[�B�S�čŕn�B�̓��B���u�ł��������������B�v�Ƃ��Ēm��n�����B�l��9��l�̓��S�ŋߔN�N�����ꂽ�i�ׂ͐l���̓�{������2��1�猏�B30���̑i�ׂŔ퍐�ƂȂ��Ă����ǂ�����قǂ��B�|�����������m�[�X�_�R�^�B�ɓ]����������t�́A�u���҂�u������ɂ���̂͂炢�B���ӔC�Ɣᔻ����Ă��ی������ł͈�҂͑������Ȃ��v�Ɛ��𗎂Ƃ��B
�@�č���t��͔�������ی��|�����ȂǂɊ�Â���19�B���u��@�B�v�Ɏw��B�y���V���x�j�A�B�ł͌ċz�����A�_�o�Ȉ�A�Y�Ȉ�Ȃǖ�1,100�l�̈�t���p�ƁA�]���Ȃǂ�������ꂽ�B��t�̊Ԃň�Ê�@���������W�ꂪ�L�܂��Ă���B�u�a�C�ł����H�܂��ٌ�m�ɑ��k���܂��傤�v�B�i�Љ����Ì���̍����͓�����s�������ʂ��Ȃ����B
�R�����g
�@��Î��̊֘A�̑i�ׂ┅���z���}���A��t�������|�����������A�x�����ɑς����˂���t���p�Ƃ�ړ]�ɒǂ����܂�A��ÃT�[�r�X�ቺ�n�т��o�����Ă���Ƃ����ł��B��s�@���̋}���f�@�˗��̃A�i�E���X�ɑ��āA�i�ׂ��|������Ή����Ȃ��Ɩ��������č��؍o�����������{�l��t���v���o���܂����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�č��̑�ֈ�Â̍��܂�@�@�|�I�A�w���A�����A�A���Ɍ��\�@�i2003/08/14�j
�@��ֈ�� (alternative
medicine)�́A����I���m��Âɑ���u��r�I�}�C���h�ȁv�A�����Ă������嗬���O�ꂽ��Â��Ӗ����邱�Ƃ������悤�ł��B�I�A�w���A�����A�A���Ɍ��Ȃǂ���̗�ŁA�����͓��m�Ƀ��[�g�̂����Â������X���ɂ���܂��B
�@�č��ł́A1998�N����2000�N�܂ł̂������Q�N�ԂŁA��ֈ�Â����a�@�͂Q�{�A�S�Ă�15.5���̕a�@�����݉��炩�̑�ֈ�Â���Ă���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��������������{�Ȃǂ̑�ֈ�Â̗��j�̒������͂������A��ֈ�ÂɐϋɓI�ȃh�C�c�Ȃlj��B�̍��ɔ�ׂĂ��č��̑�ֈ�Â̕��y�͂܂��܂��A�Ƃ����̂��{���̂Ƃ���ł��傤�B
�@��ֈ�Â͂قƂ�Lj�Õی��ł̓J�o�[����Ă��܂���B�������A���ݕč��̐l��270���h���Ƃ������z�N������ł��܂��B���̃}�[�P�b�g�̑傫���ɒx�܂��Ȃ���a�@�����ڂ���������Ȃ��Ȃ����B�ŋߑ�ֈ�Â��s���a�@���}�������w�i�ɂ͂��̂悤�Ȍo�ϓI�Ȕw�i������A�Ƃ����������͂��s�����̂�����悤�ł��B�a�@�Œ�����Âɂ��I���ÁA�����N�Z�[�V�����A���K�Ȃǂ�����A�����͌����Â̕���p�̌y���▖���̊��҂�����u�Ɏ��Âɍs���Ă��邱�Ƃ������悤�ł��B�a�@�̑����͗��s�̑�ֈ�Â���荞�ނ��Ƃɂ���ė��v�𑝂₻���Ǝv�����悤�ł����A�����ɂ͂��܂���v���オ���Ă��Ȃ��悤�ł��B��Õی��ɃJ�o�[����Ă��Ȃ��̂ŁA�T���Ȋ��҂�����ֈ�Â𗘗p�ł��Ȃ����Ƃ��傫�ȃl�b�N�ɂȂ��Ă��܂��B
�@����a�@�̃X�|�[�N�X�}���̓j���[���[�N�^�C���Y�̋L�҂ɐ������A�u�Ⴆ�}�b�T�[�W���Â͊��҂������b�N�X���ċC�����悭����̂��ړI�ŁA�}�b�T�[�W���̂��̂����w��p���N�����A�Ƃ��咣�������͂���܂���v�B�������A���̕a�@�̊��҂���p�̃p���t���b�g�ɂ͂�������u�}�b�T�[�W�͑̂���őf����菜���A�Ɖu�͂����߂��p������܂��v�Ə����Ă���A�L�҂�������܂����B���̍��̓j���[���[�N�^�C���Y03/04/13���Q�Ƃ��܂����B�@�i���[���}�K�W���č���Â̌��ꂩ��@����̔����j
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
��p�{�݊�̍������s�\���@�@���㋦�E�Z�p�]�����ȉ���@�i2003/11/17�j
�@�@ ���㋦�̐f�Õ�V�������g�D�E��ËZ�p�]�����ȉ�͕���15�N11��17���Ɏ�p�̎{�݊�Ɋւ��āA�G�r�f���X���s�\���ŋZ�p�W�ϐ��Ǝ�p���т̑��ւɊւ���u����Ȃ�f�[�^�̎��W���K�v�v�Ƃ̒��ԕĂ��������B
�@���ȉ�ł́A���㋦������14�N����Ŏ�p�{�݊������ۂɑO��Ƃ��Ă����Z�p�W�ϐ��Ɛ��т̑��ւɂ��āA���J��q�F���i�����ی���ÉȊw�@����Ȋw�����j�́u��Â̎��ƋZ�p�W�ϐ��Ɋւ��錤���v��A10��31���̉�ŕ��ꂽ�O�ۘA�̒������ʂ���ɋc�_�����B���J�쎁�́A�n�悪��o�^�A�݂�����݂̈���o�^�ȂǂV�̃f�[�^�x�[�X��p�������v���͂ɂ��u�{�ݓ�����̎�p�����Ǝ�p���ʂɓ��v�I���ւ��F�߂�ꂽ�v�Ƃ����B�������ψ��̊Ԃ���A���̌����Œ����ɋZ�p�W�ϐ��Ɛ��тɂ��ăG�r�f���X������ꂽ�Ƃ��邱�ƂɐT�d�Ȉӌ����o����A�g�c���ȉ�����J�쎁�̈ӌ��������܂ŎQ�l�ӌ��ɗ��߂�l�����������B
�@�@�O�Ȍn�w��Љ�ی��ψ���A���i�O�ۘA�j��031113�A�����s�ŊJ���ꂽ���{�Տ��O�Ȋw��̒��ŁA����14�N�f�Õ�V����œ������ꂽ��p�̎{�݊�ɂ��āA�e�s���{���Ɋ�����{�݂̂Ȃ���p�Q���������邱�ƂȂǂ𖾂炩�ɂ����O�ۘA�A���P�[�g�����Ȃǂ���ɁA�u�ꎞ�������ׂ����v�Ƃ̍l�����������B�����A�{�݊�̕K�v���͔ے肹���A�u�Ȋw�I�����̂���{�݊���������ׂ����B���㐧�x�����e���ᖡ������Ŋ��p���ׂ����v�ƒ�Ă����B
�@���{��t��̐�����́A���㋦�f�Ñ��ψ��Ƃ��āu��p�ɌW��{�݊�p�~�v�����߂Ă��邱�Ƃ�����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
������9��w����w�E���w�a�@���A�@6��w�͕a�@�����u��C���v�@�i2003/10/03�j
�@��w�������a�@�Ǝ��w�������a�@�������Ă���9�̍����傪�A10��1�����痼�����a�@�����A�V���ȓ���@�\�a�@�Ƃ��ăX�^�[�g�������B
�@�������a�@�������Ă���������a�@�́A�k�C����E���k��E�V����E������Ȏ��ȑ�E����E���R��E�L����E������E��B��E�����E���������11��w�B���̂����A������Ȏ��ȑ�Ƒ��������9��w�̕a�@���������ꂽ�B
�������ꂽ�a�@���́A���k�傪�u���k��a�@�v�A�V���傪�u�V����㎕�w�����a�@�v�ƂȂ����ȊO�͂��ׂāA�u�������w�����w�������a�@�v�ƂȂ����B
�@���̓����ɔ����A�a�@���E�Ƌ����E�C���Ȃ��u�a�@���̐�C���v�����{�����̂́A
�k��E�V����E�L����E������E���E���������6�̑�w�a�@�B ���ȏȂ́A�@���E���C��̋����E�ւ̕��A�͑�w�̍ٗʌ��Ƃ��Ă��邪�A�������w�����w�������a�@�́A�a�@���E�����R�[�����������E�ւ̕��A�͂ł����A���E���邱�Ƃ�����a�@����C����~�����B����̏ꍇ�A�a�@����C�������̕��j���A�S��������s�������A��]�҂����ꂸ�A7�����̋�����ŕa�@���I�������{�B���E�̈�w�������a�@�����������쐪����I�o���Ă���B
�@
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�㔭��̉��i������Ɉ����@�u�V��̂W���v�������ց@�i2003/11/28�j
�@�����J���Ȃ̒����Љ�ی���Ë��c��i���㋦�j��啔���03/11/28�A���������ꂽ�V��Ɠ������Ŋ����Ȍ㔭�i�̉��i������Ɉ��������邱�Ƃ𒌂Ƃ���2004�N�x�̖���Ɍ������Z����@�̌������Ă��܂Ƃ߂��B
�@�߂����㋦����ɕ���B��̓I�ȉ������Ȃǂ͓�����ŔN���܂łɌ�������B�㔭�i�͐V��ɔ�����J����قƂ�ǂ�����Ȃ����߁A����܂ŐV���ɕی��K�p����鎞�̉��i�͐V���8���ƌ��߂��Ă����B������������̒����ł́A2000-01�N�x�ɔ������ꂽ�㔭�i�̖́A�������i�̉����ɂ��A02�N�x�̉���ŕ��ϖ�4���Ƒ啝�Ɉ���������ꂽ�B�u�V���8���v�Ƃ������艿�i�����Ԃɍ���Ȃ����̂ɂȂ��Ă����B�l�������ɂ��āA�������Ắu���苟������̏[����}��K�v���܂��Č�������v�Ƃ��Ă���B
�@�V��̉��i���̊O���ł̖̕��ω��i����ɒ���������@�ɂ��ẮA���鍑�̖��ɒ[�ɍ����ꍇ�͒������@���������A�Ƃ����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
��Ƃɂ��Ă̘b��
�P�A��Ɛi�� �@�i2003/10/08�j
�@�a�@�����҂ɏ���������o���A�O���̖�ǂ����n���u�@�O�����v�����߂Č܊����A��Ƃ��i��ł��邱�Ƃ�����15�N10��9���A�����J���Ȃ����\�����u2002�N�Љ��Ðf�Ís�וʒ����̊T���v�ŕ��������B
�@�����A�@�O�������́A�a�@�ł�53.7���i�O�N��8�|�C���g���j��5���������A�f�Ï���42.3���i��2.6�|�C���g���j�ŁA��Ë@�֑S�̂ł�46���i��4.5�|�C���g���j�������B
�@���҈�l�̈�����̖�ܔ205�~�ȉ��Ȃ��ܖ���f�Õ�V�����i���Z�v�g�j�ɏ������ɐ����ł���u205�~���[���v����N4���ɔp�~���ꂽ���߁A��ܖ���������Ă��Ȃ���ܔ�̊����͑O�N��52.4������3.6���ɑ啝�Ɍ��������B��Ô�ɐ�߂��ܔ�̊����͑O�N��0.9�|�C���g����21.6���ƂȂ����B
�@�����͍�N6���A�S����14000�J���̈�Ë@�ւ��ǂ��猒�N�ی��g���⍑�����N
�ی��Ȃǂɏo���ꂽ���Z�v�g�̂�����50������ג��o���čs��ꂽ�B
�Q�A��Ƃ̕]���@�u�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�������@�@�i2003/06/01�j
�@���ۘA�́u��Ƃɂ���܋��t�̍������Ɋւ��钲���������Ɓv�̃A���P�[�g���\�����B�@�O�����ɂ��Ă͔����߂����u�i�悢���������j�ǂ���Ƃ������Ȃ��v�ƉA�]������ӌ��Ƃ��ẮA�u��t���ڂ������������Ă��ꂽ�v�u�҂����Ԃ����Ȃ��Ă��v�Ȃǂ������̂ɑ��A�ے�I�Ȉӌ��ł́u�Q�x��Ԃ������v�u�i�@���������j�x���z�������Ȃ����v�Ƃ��Ă���B
�R�A���ܖ�ǂƂ̘A�g�̓���@�i2003/06/01�j
�@�D�y�s�ŊJ���ꂽ��26����{�v���C�}���E�P�A�w��i����ђˍO�u�k�C����t��A����15�N�U���j�ŁA���҂ւ̈��i�����e�[�}�ɂ����V���|�W�E�����s��ꂽ�B���̒��œ����̐f�Ï���Ώۂɍs�����A���P�[�g���ʂ\�B���ܖ�ǂ��厡��Ɏ��Â̈Ӑ}���m�F�����Ɋ��҂ɏ�����̕��~���w������P�[�X�����Ȃ��Ȃ��ȂǁA�@�O�����ɂ������ǂƂ̘A�g�̓���������яオ�����B�A���P�[�g�͓�����3080�f�Ï��ɑ��Ď��{���A1448�f�Ï�����L�����B����ɂ��ƁA�@�O�������s���Ă���f�Ï���46���A�@��������44���A���p��9���B
�@�@�O�������s���Ă���f�Ï��ɁA����������i�̏��̕��@�����Ƃ���A�u�O���ň�ʂ�������ď���Ⳃs�v���ߔ������ł������A�u�������闝�R�͐������邪�A��̓I�����͖�ǂŁv�͂S�����B����A�u�������ύX�������͂��̓s�x�����v���Ă���f�Ï��͂T���Ə��Ȃ��A�u��ؖ�ǂɔC���Ă���v�f�Ï����U���������B�@�O�����Ɋւ��ẮA�u��t������������D�]�v�u�������Ԃ��Z���Ȃ�A�f�Âɗ]�T���ł���v�Ȃǂ̃����b�g�̂ق��A�u���߂Đ��������߂���v�u��ǂł̐��������Â̏�Q�ɂȂ�v�u���҂����p���S���������Ƃ����N���[�����������v�Ȃǂ̖��_���w�E���ꂽ�B���ɁA�u���Â̈Ӑ}�Ȃǂ��厡��Ɋm�F�����ɁA������̕��~���w�����ꂽ���Ƃ�����v�Ƃ������������Ȃ��Ȃ������B
�R�����g
�@��Ƃ́A�a�@�E�f�Ï����{�ݓ��̖�ǂœ��邱�Ƃ���߂ĉ@�O����Ⳃs�A���҂͍s�����̒��ܖ�ǂŏ�������w������Ƃ������́B��Ë@�ւ̉ߏ蓊��̗}���A���ܖ�ǂɂ�銳�҂̓�����̈ꌳ������i���̒Ȃǂ�ړI�ɓ�������܂����B�������A�����������Ă���悤�ł��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
���@��Â̕�]����15�{�݂ɔ����@�i2003/04/03�j
�@����@�\�a�@���̓��@��Â̕�]�����x��1�����珇���X�^�[�g�������A���ۂ�4�������]��������̂�15��w�a�@�E�i�V���i���Z���^�[�ɂƂǂ܂�B2���̒��㋦�œ���@�\�a�@���̕�]�����x�ɂ��āu4�������\��v�Ɖ����v31�̍������E������w�a�@�A�i�V���i���Z���^�[�̂����A�u4�������v�ɂ��������̂�15�{�݂ŁA�����\��̂قڔ����ɂȂ����B1�������]�����x�������̂́A
������a�@
�@�Q�n��a�@�E������Ȏ��ȑ�a�@�E�R����a�@ �E����a�@
�E��������a�@
������a�@�@
�@�D�y��ȑ�a�@�E���s����a�@
������a�@
�@���a��a�@�E�������b���ȑ�a�@�E���}���A���i��ȑ�a�@�E���c�ی��q����a�@�E�ߋE��a�@�E�Y�@�ƈ�ȑ�a�@
�i�V���i���Z���^�[
�@��������Z���^�[�����a�@�E�����z��a�Z���^�[
�̌v15�{�݁B
�@2�����_��4��������\�肵�Ă���������a�@�̂����A������a�@�A�R�`��a�@��5���ɁA�����ȑ�a�@�A���R��a�@�Ȃ�4��w�a�@�Ɩh�q��ȑ�a�@��6���ɁA�V����a�@��7���ɂ��ꂼ��ύX�B������w�a�@�ł́A���s�{����ȑ�a�@��4��������f�O���A7��1���ɓ�������\��ŁA�n���Љ�ی������ǂɓ͂��o�Ă���B
�@����4��������\�肵�Ă���13�̎�����w�a�@�̂����A7��w�a�@��5���ȍ~�̉��������߂����A���̂���������ȑ�a�@�́A3��31���܂�4�������̉\���ɂ��ĉ@���Ō������A�ŏI�I��1�����������邱�Ƃ�I�����ē͂��o���B����a�@�W�҂́A�u4�����{���߂��������A���ʓI�ɏ������Ԃɍ���Ȃ������B��a�̑I���������v�Ƃ��Ă���B
�R�����g
�@���@��Õ�]���̕���15�N4�������͂ǂ��ɂ��n�܂����悤�ł��B�����̎{�݂ɂ�������{��̈�Ó��e�̕ω��E���Җ����x�Ȃǂ��Q�����\����Ă������̂Ǝv���܂��B���̈�Ë@�ւ֓����̂������\��������̂Ƃ��āA���ڂ���K�v������܂��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
����v�����F�@�i2003/03/12�j�@
�P�A�u���R�f�Áv�Ɓu���x��i��Áv�Ɍ����Ċ�����ЎQ��OK�@
�@����15�N2��27���A�\�����v����Ō��I��Õی����K�p����Ȃ����R�f�ÂɌ���A��Ë@�o�c�ւ̊�����ЎQ�����F�߂�ꂽ�B����Y�́u�V��������̈�ÃT�[�r�X�ɕK��������v�Ƃ��Ă��邪�A��]���Ă���̂͒��쌧�����ŁA���҂ւ̃����b�g�͏��Ȃ��Ɨ\�z�����B
�`�A�@���R�f�ẤA���I��Õی����g���Ȃ������⎡�Â̂��ƁB����������p�͑S�z���ȕ��S�ƂȂ�B���e���`�⌒�N�f�f�Ȃǂ�����B���҂ɂƂ��ă����b�g�́A�f�Õ�V�ȏ�̌����⎡�ÁE�Ō삪���A���ޗ�����荂���Ȃ��̂��g����B�������č��̂悤�Ɏ��R�f�Â���舵�����ԕی��ɉ������Ă��Ȃ��ꍇ�͑S���̎���ƂȂ�B
�a�A�@���x��i��ẤA���J�����F�߂���������⎡�Â��ł���Ö@�̂��ƁB���x���̍�����ËZ�p��{�݂����Ă�����菳�F�ی���Ë@�ւł������{�ł��Ȃ��B���݁A���x��i��ÂƂ��ĔF�߂��Ă���̂́A�]���ɂ��S���̈ڐA��p�A�Ō`��ᇂ̂c�m�`�f�f�A���[�U�[���nj`���p�Ȃ�65��ށB���{�ł����Ë@�ւ͑�w�a�@�Ȃ�97�{�݁B
�b�A�@���x��i��Âɂ��ẮA�u����×{��x�v�A��Ô�̈ꕔ���ی����t�A���z�������ȕ��S�z�͕ی�����o��Ȃǂ̐��x������A�S�z���ȕ��S�̊�����Ђł͋����ɂȂ�Ȃ��B���̂܂܂ł́A���菳�F�ی���Ë@�ւ��鍂�x�ŗǎ��Ȉ�Â����邱�Ƃ��A������Ђ̐����Ȃ������b�g�ƌ����������B
�c�A�@���{�Ŋ�����Еa�@���������낷�ɂ́A���I��Õی��Ɏ��R�f�Â�g�ݍ��킹�邱�Ƃ��ł���u������Áv�̓������K�v�����A���������J���W�c���Ȃǂ������Ă���B
�Q�A�O���l��t�̎���ɘa
�@�����J���Ȃ͕���15�N2��21���܂łɁA�O���l��t�̎���Ɋւ���K����S���ꗥ�Ɋɘa������j�����߁A���{�̍\�����v���搄�i���ɓ`�����B�O�����{�Ƌ��c���ēԂň�t�h������茈�߂錻�݂̘g�g�݂͎c�����܂܁A���݂Ɏ����d�g�݂����߂āA�n�������̂Ȃǂ̗v�]�ɉ����ĊO������̈���I�Ȉ�t�̔h����F�߂�B�����A
�`�A�@���{�̈�t�Ƌ��ɏ��������i�����ɍ��i
�a�A�@���������O���l��t���f�Âł���̂͊O���l�����œ��{�l�͑ΏۊO
�Ȃǂ̋K���͎c�����j�B
���J�Ȃ͏]���u��t�Ƌ���L���Ă��Ȃ��҂̈�Ís�ׂ͊��҂̐����A�g�̂̊댯���v�ƋK���ɘa�ɔ����Ă����B���������쌧�Ȃǂ��O���l��t�̐f�Â��\�ɂ��������āB���r�˔�����S��������Õ���ȂǂŁu�[���v�̑������J�ȂɋK�����ɂ߂�悤�������߂Ă��邱�ƂȂǂ��āu����O�i�v�i���J�Ȉ㎖�ہj�̑Ή��ɓ��ݏo�����B�����A���i���́u���̓s�x�A�ԂŎ�茈�߂�����͉��߂�K�v������v�ƈ�w�̋K���ɘa�����߂Ă���A����̋Ȑ܂��\�z�����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
���ی���10���l�グ�ց@���N�x�A����3200�~�ɁA�n��Ԋi���͊g��@�i02/09/18�j
�@����15�N4���Ɍ������\���65�Έȏ�̐l�ɑ�����ی����ɂ��āA�S���̕��ϕی����z�i��z�j�����s��2900�~����3200�~���x�ցA��10���l�グ����錩�ʂ��ł��邱�Ƃ�����14�N8��7���A�����J���Ȃ̒��ׂŕ��������B����҂̑����ɔ������ی��̃T�[�r�X�ʂ��L�т�̂��m���Ȃ��߂ŁA�Ꮚ���ґw�ɂ͂���ɏd�����S�ɂȂ肻�����B�ی����z�͂����܂Ō��݂̉���V�P���ȂǂɊ�Â��b��I�Ȑ��l�B���̂��ߓs���{���ɂ���Ă͋�̓I�Ȍ��\�����̂Ƃ���T���Ă��邪�A���J�Ȃ́u�S�̓I�ɂ�10�����x�l�オ�肵�������v�ƕ��͂��Ă���B
�@�����ۂ������ʐM�����{�����s���{���ی��������ɂ��ƁA���ό��z���ł������̂͐X�Ō��s��3256�~����3800�~�ɏオ�錩�ʂ����B�܂����N4������̕ی����ł͉��R3689�~�A���s3600�~�A���m3572�~�A���3435�~�Ƒ����B����҂̑����ɔ����v���x��F�肷�銄�������������ق��A�����Ԏ���₤���߂Ɏ肽�������艻����ւ̕ԍς��ی����ɒ��˕Ԃ����̂��e�������悤���B�t�ɁA���ό��z���ł��Ⴂ�̂́A������2570�~�A�ȉ��{��2835�~�A��t2872�~�A��2924�~�ȂǁB�s�������Ȃǂ͖��炩�łȂ����A�ō��z�ƂȂ����̂͐X������5850�~�A�����ō��m������5110�~�B�Œ�z�͋{�錧����1124�~�ŁA�T�[�r�X�̐��������Ă��Ȃ����߁B�����Ŋ�����1531�~�������B
�R�����g
�@���ی��̓T�[�r�X�̗��p��������Εی����͏オ��d�g�݂ɂȂ��Ă���A������i�ޒ��A�l�グ�͊���H���Ƃ�����B�W�҂���́u�悭10�����x�̒l�グ���Ŏ��܂����v�Ƃ̎w�E���o�Ă���B�ʂɌ��Ă�����6000�~��ƍ��z�̕ی�����������ł���ی��ҁi�����́j������A�n��Ԋi���͍L�������B���݁A�e�ی��҂͗��N�x����܃J�N�̎��ƌv�����i�߂Ă���B�ی������S�Ɨ��p�҂̃j�[�Y�Ƃ̃o�����X��}��Ȃ���T�[�r�X�̊�Ր����������ɐi�߂邩�A������肪���ڂ����B�ی������オ�葱���Ă����ȏ�A�ی������̈���Ɍ����A�ꕔ�����g���Ȃǂɂ������̍L�扻��s���������̎��_���������Ȃ��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�a�@�I�с@�Ǘᐔ���p�����Ȃǂ�ڈ����@�@(2002/05)
�@�ǂ̈�Ë@�ւŎ�p�Ȃǂ̎��Â���̂��A�����߂�ڈ��Ƃ��āA�a�@���肪������p�����Ȃǂ́u�Ǘᐔ�v�����ڂ���Ă���B�����J���Ȃ͂S������A��Ë@�ւ��L�����Ă悢���ڂɏǗᐔ�荞�݁A��Ô�̕ی��_���̎Z��ɂ��ꕔ��������B
�P�A���ÏǗᐔ�Ǝ��Ð���
�u���{�S���a�@�\���͓x�����L���O�v���Q���ɔ��s���ꂽ�i�Ёj�B�u�a�@�u�����h�łȂ��A�Ǘᐔ�őI�ׁv�ƕ��肪�������̖{�̓A���P�[�g���ʂ����Ƃɕa�@�����a���p�@���Ƃɕ��ׂĂ���B�Ǘᐔ�Ǝ��Ð��ʂ̊֘A�������炩�ȕa�C�̓����L���O�v�Z���A�܂��֘A�����s���ȕa�C�⎡�Âɂ��ẮA�f�[�^�����̂܂܌f�ڂ��Ă���B
�Ĉ�w�������ɂ��ΐS���o�C�p�X��p�A����O�Ȏ�p�A�G�C�Y���Âł͏Ǘᐔ��������Ë@�ւ��t�́A���Ð��т��ǍD�Ƃ��ꂽ�B���ɂ���������A�H������̎�p����̎��S���͂Q�`�R�{������B����܂ł̌����ł́A�l�H�߁A�����؏��Ȃǂɂ��֘A�����݂���Ƃ����B
�Q�A���{�ɂ�����Ή�
�����Ȃ͂S������A��p�����Ȃǂɒ��ڂ�����̐��x����������B��́A��p�����Ǝ��a���Ƃ̎�f�Ґ��Ȃǂ���Ë@�ւ��L���ł���悤�ɂ����B������͂��܂�ɂ����������Ȃ���Ë@�ւɂ͎��Â��������Ă��炤���߁A�O�N�x�Ɍ��߂�ꂽ�����i�T���`�P�O�O���j�����{���Ă��Ȃ���Ë@�ւɂ́A�f�Õ�V�̂V�������x����Ȃ��Ƃ������́B
�R�����g
�@�����V��(02/03/21)�̋L���̗v��ŁA�g�ǂ���t�E���܂��O�Ȉ�A��Ë@�ւ̌��������h�Ɋւ���b��ł��B�O�Ȉ�̈�l�Ƃ��Ď��͊O�Ȉ�̏Ǘᐔ��Z�p�Ɋ֘A���Ĉȉ��̂悤�ɍl���܂��B���ꂼ��̊��҂���̏�Ԃ��قȂ邽�ߊO�Ȏ��Â̐��т̔�r�͈�ʂɍ���ŁA�O�Ȉ�̌o�������Ǘᐔ�����̑�p�Ƃ���̂͑Ó��ȕ��@�̈�ł��i����䂦���̂g�o�ł��g���̗Տ����сh�Ƃ��Č��J���Ă��܂��j�B�g�O�Ȉ�̏Ǘᐔ�h�͂��̌o����Z�p�̔��f�ƒ����I�ɂ��������₷���킯�ł����A����ɑΉ�����g�u�a�@�́v�o����Z�p�h�ɂ͕s�N�����������ɂ���܂��B�]���āg�a�@�̏Ǘᐔ�h���Q�l�ɂ���ۂɂ́A�N�̏Ǘᐔ���i�����̊O�Ȉ�̏Ǘᐔ���W�߂��ꍇ�͕��G�ɂȂ�܂��j�A���݂̍ݐЏ�ԁA�Ȃǂɗ��ӂ���K�v������܂��B
�O�Ȉ�l�̋Z�p�Ǝ��ÃO���[�v���̂̋Z�p�Ƃ̊W�ɂ��Ă͈ȉ��̂悤�ɍl���܂��B�i�s����������ᇁA�d�x�̍����ǁi���A�a�E�z�펾���E�t�������Ȃǁj���ꍇ�Ȃǂł́A�O�Ȉ�̋Z�p�ȊO�̔�d�i�R���܂�Ɖu���ÁE�ɂ݂ւ̑Ώ��E�e����ʑΉ��j�������Ȃ邽�߁A���Ð��т̓O���[�v�̐��т��ǍD�ȑ����a�@��I������̂��Ó��ƍl���܂��B�����ۂ��A�ǐ���ᇁE�a�C�ɂȂ�������ւ̑Ώ������Ŏ��Â��������鏉���̈�����ᇁE���Ǐ�Q�Ȃǂł́A�O�Ȉ�̋Z�p���傫�ȗv�f�����߂܂��B���O�ȕa�@�i�]�_�o�O�ȕa�@�A������O�ȕa�@�Ȃǁj�ŏ[���ɑΉ��ł���Ǝv���܂�����A�����̐v�����E�ʉ@����މ@�̕X�E�T�[�r�X�̑��ǂȂǂ��l����]�n������܂��B
���e�i�ڎ��j�֖߂�
�p���A����ŊC�O�Ŏ�p���@�|��Î����s�������O�ʼn����[�@(2002/05)
�@����Ŏ�p����ɂ͂P�N�ȏ���҂������p���ŁA�����S�z�S���C�O�Ŏ�p�����Ȑ��x���n�܂�A���w9�l��02/01/18�A�p���C���g���l�����t�����X�Ɍ��������B9�l�͉p�쓌���P���g�B�̏Z���ŁA�t�����X�k�����[���̕a�@�ō���G�A������Ȃǂ̎�p����B3���܂ł�200�l�O�オ���̐��x�𗘗p����\��ňꕔ�̓h�C�c�ł���p����B
�@�p�����ł͍������N�ی��̓K�p��������Ύ��Â͖��������A��t��Ō�w�s���̂��ߒ����Ɏ�p����ɂ͗L���̎��c�a�@�ɍs�������Ȃ��B���c�a�@�ł̔�p�����S����悤����ꂽ���́A�ނ���O���̕a�@�𗘗p���Ă�������������オ��Ɣ��f���A��N�H�V���x�̓��������߂��B
�@���҂����͎�p�o��A����A�p��̃A�t�^�[�P�A�̔�p���܂߂Ă��ׂč����o�����A�t���Y���̉Ƒ��̗���Ɋւ��Ă͎��ȕ��S�Ƃ��Ă���B
�R�����g
�@�T�b�`���[���k�������p����Â��u���C�A�������A��������܂����A���݂̈�ÃT�[�r�X�͐�ΓI�ɕs�����Ă���悤�ł��B�V���ɂ́g��Ȑ��x�h�Ə����Ă���܂������A���S�Ǘ��⊳�Ғ��S�̌������т��Ă���A�����̐�������A�N�Z�X���₷�����d�����A�{�݂̉ߕs�����s�ꌴ���Œ��߂���Ƃ����A�O���[�o���ō����I�ȉ^�p�Ǝv���܂��B���{�̈�Â̕������ł���A�g���Ȋ����^��Â���A�@�\�����ɂ���ØA�g�ɂ��A��Â̎��E�����E�����̌�����͂���n�抮���^��Âցh���A���łɍ����i�d�t�j�̘g���z���Ď������Ă���Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B
���e�i�ڎ��j�֖߂�
e�w���X�@���{�ł��g��̋@�^�@�@�\���ҁE��t�̊W���ω��A�V�����ۑ���[
�@(2002/05)
�@�a�C�⎡�ÂɊւ�������C���^�[�l�b�g�Œ��ׁA��t�ƃI�����C���ł��Ƃ肷��u���w���X�v�����{�ł������o�����B���҂���̓I�Ɉ�Âɂ�������t�E���҂̊W�����P�ł���Ƃ������҂̈���ŁA���̍�������ł��邩�ȂǁA�ۑ�������B
�P�A�\��V�X�e���u���׃N�C�b�N�v�̗��p��@�|�f�f���Â��T���ɒZ�k�\
�@�u���׃N�C�b�N�v�́A�p�\�R���Ŏ�f�\������鎞�Ɂu�M�͂���܂����v�Ȃǂ̎��O��f�ɓ�����B��t�͎��O�ɏ�����͂��Ă��邽�߁A�T�����x�Őf�@�E����܂ŏI���B�\��V�X�e�������肵���f�f��60-70%
�͐��m�ł������Ƃ����B����z�e���̃`�F�b�N�C���E�`�F�b�N�A�E�g�̎葱������������������悤�Ȃ��̂ŁA�{���̈�ÃT�[�r�X���d�����鎎�݂ƍl������B
�Q�A���w���X�֘A�s��A�č��ł͓������n�܂�
�@�č��ł́A��N1.6���~���������w���X�֘A�s�ꂪ�A2005�N�ɂ�3.7���~�ɒB����Ƃ̗\��������B���̒��S�́A�s�������Ɍ��N�E��Ï��A�܂���t��ɍŐV�̌��������Ȃǂ����C���^�[�l�b�g�̃T�C�g�����A���ɓ������n�܂��Ă���B�u�E�F�u�G���f�B�v�i�����s������j�͍�N�Ăɕč�������{�ɐi�o�����B���{�ł͌��N��������Ė����l�������A�C���^�[�l�b�g�͐��m�Ŏ��̍��������o���̂ɍD�s�����Ƃ��Ă���B�č��ł͈�t�ȊO�̈�ʎs�������Ŗ�����疜���ȏ�̃A�N�Z�X������V�F�A�P�ʂ̃T�C�g�����A���{�ł͓��ʁA��t�����ɍi����j�Ƃ����B
�R�A���{�ň�É��v�̋N���܂ƂȂ邩
�č��ł̓C���^�[�l�b�g�̕��y���u����������R�X�g�Ȉ�Áv�ւ̃j�[�Y�Ɍ��т����B�������u�L���ȃT�C�g���A���z�̌f�ڗ����������Ë@�ւ�D��I�ɏЉ���v�u���ҏ��̘R�k�v�Ȃǂ̎�����������Ă���B�u���w���X�v���v�i���{��Ê�抧�j���o�ł������{�C���^�[�l�b�g��Ë��c��́A���ゅ�w���X�̕��y�͈�É��v�̋N���܂ɐ��蓾�邪�A���p�҂̈��S��v���C�o�V�[�̊m�ۂ��d�v�Ƃ��Ă���B
���e�i�ڎ��j�ւ��߂�
��ȑ�w���w�a�@�A�������@(2002/05)
�@�����Ȋw�Ȃ͕���13�N12��21���ɓ������ꂽ2002�N�x�\�Z�ĂŁA���N10���̎R����ƎR����ȑ�̓������F�߂�ꂽ�Ɣ��\�����B���̑��A2001�N10��10�����_�ň�ȑ�w�W�œ����������E���c���̎{�݂͎��̒ʂ�B�����E������i03�N�̓������������j�A�x�R��E�x�R��Ȗ�ȑ�A�����E�����ȑ�A�����E�����ȑ�A������E������ȑ�A���m��E���m��ȑ�A�����E�����ȑ�A�啪��E�啪��ȑ�A�{���E�{���ȑ�B
�@��B��͕���14�N2��19���A�����s�ɂ����w���t���a�@�Ǝ��w���t���a�@�A�ʕ{�s�ɂ��鐶�̖h���w�������t���a�@�̎O�a�@��������j�����߂��B�����͍Ő�[�̈�Â̎��{�A���N�Â���̂��߂̕��L���T�[�r�X�A�Ɨ��s���@�l���ɔ����ẴR�X�g���팸�Ȃǂ̑_��������B�����Ȋw�Ȃɂ��ƁA��w�a�@�����͍L����A������Ȃǂł��v�悳��Ă���B
���e�i�ڎ��j�֖߂�
���/ �҂����Ȃ��̉��v�@�@�@1��ځ@���傷���Ô���ǂ��}���邩�@�@(2001/10)�@
�P�A��Ô�̗}��
�@�K�����N�`���̎��Â��邽�߁A���[�Y����͕Г��T���Ԃ������ĊO���ʉ@���Ă���B�܂��q�U�̔����̎�p�����A��ōs����B�a�@�͂ł��邾���A��Â̖��ʂ��Ȃ����Ċ��҂𑁂��މ@�����悤�Ƃ��Ă���B����͂P�X�W�R�N�Ƀ��[�K���哝�̂����������c�q�f�^�o�o�r�Ƃ������x�����������ƂȂ��Ă���B���̐��x�͊��҂̕a�C���Ƃɂ��炩���߈�Ô���܂��Ă��āA����ȏ�͐����ł��Ȃ��d�g�݁B����ɂ�蕽�ύ݉@������
5.9 ���Ɠ��{�� 1/5�ȉ��ƂȂ��Ă���B�����ЂƂ��}�l�[�W�h�E�P�A�Ƃ����ی��V�X�e��(���ԕی������҂̂W�O�����������Ă���)�B����͕ی���Ђ������̈�t�ƌ_������сA��Ís�ׂɖ��ʂ��������������Ǘ�������́B�ی��ɉ����������҂͌����A�_���t�ɂ���������Ȃ����ی����͒�z�ł��ގd�g�݁B
�Q�A�}���̌���
�@��Ô�}������钆�A�a�@�͎������m�ۂ��邽�߁A�ϋɓI�Ȍo�c�w�����s���Ă���B�܂��a�@��I�Ԋ��҂̖ڂ��������Ȃ�A�a�@�̊i�t�����s���G����z�[���y�[�W������A�a�@�Ɋւ���l�X�ȏ�����Ă���B
�@���������ʂ��Ȃ����Ƃ��邠�܂�A�\���Ȉ�Â����Ȃ����҂����ꂽ�B�������Ă����̂̓}�l�[�W�h�E�P�A�^�̖��ԕی��ŁA������t�����߂鍜���ڐA�͋��ۂ���A���F�܂łɎ��Ԃ����������B�S�čő�̊��҂̌����i��c�̃t�@�~���[�Y�t�r�`�ł́A�s���߂�����Ô�}�����͈�Â̎���ቺ�����Ă��܂��ƁA�����Ƃ����Ɋ��Җ{�ʂ̈�Â�����������ׂ������������s���Ă���B�܂��Ⴂ��t�ւ̋���ɗ͂𒍂�������A����̈�t���T�C�U�N�Ɉ�x�A�f�f�\�͂�]�������V�X�e�������{�����ȂǁA��Ð�����ۂw�͂��s���Ă���B
�R�����g
�A�����J�ł́A��Ô�̐L�т��ǂ��ɂ��}�����悤�ƁA���@�����̒Z�k���Ô�̒�z�����̓����Ȃǂň��̐��ʂ����Ă��܂��B���̈���ŕK�v�Ȉ�Â܂Ŏ��Ȃ��Ƃ����}�C�i�X�ʂ������яオ���Ă��܂����B���{�̈�Ô�̗}������l����Ƃ��̋��P�Ƃ��ĈӋ`�[���Ǝv���܂��B�m�g�j�@�a�r�P�@�C���^�[�l�b�g�f�x�[�h�i01/09/22�j���܂Ƃ߂����̂ł��B(http://www.nhk.or.jp/debate
�Q�Ɓj
��Ô�}����̉e��
�P�A��Ô�̍ď㏸
�@�@�}�l�[�W�h�E�P�A�̕��y�ɔ����ĂP�X�X�W�N����ēx�㏸�����B�}�l�[�W�h�E�P�A�ł͈�t�⊳�҂��K�v�Ǝv�����Â��̔�p��ی���Ђ��F�߂Ȃ��ꍇ������A�ی���Ђƌ�����\�[�V�������[�J�[��K�v�Ƃ��A�܂��f�ÑO�Ɋm�F���邽�߂̎��O�R���X�y�V�����X�g�ȂǁA�V���Ȑl�ނ��K�v�ƂȂ������߁B
�Q�A�a�@�̌o�c�w��
�@���̂P�O�N�łS�O�O�ȏ�̕a�@�����p�����ꂽ�B�܂��A�A�M���{�ƏB���J������a�@���҂Ɋւ�����͊e�a�@�̎��S���̃f�[�^�A��p�̐������A��Ґ��A��t�̏o�g�Z�⌤�C��̕a�@�A�ݔ��̏[���x�ȂǑ���ɓn��A�����̏��͗e�ՂɎ�ɓ���B�i�t���Ɋւ���o�ŕ����������s����A���҂͏�ɕa�@�ƈ�t��]�����邱�Ƃ��ł���B
�R�A�s���߂����}��
�@���҂��K�v�Ȉ�Â����҂����Ȃ��Ƃ������Ԃ������N�������B�ی���Ђ����Ȃ��Ǘ�ւ̈�Ís�ׂ�A�ŐV�̈�Ís�ׂւ̎x���������ۂ��邱�Ƃ����邽�߁A��t�Ɗ��҂��K�v�Ȉ�Ís�ׂ�ی���ЂɔF�߂����邽�߂̌����������ƁA���҂̗e�Ԃ��������邱�Ƃ��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
���/ �҂����Ȃ��̉��v�@�Q��ځ@��Ô��N���ǂ����S����̂� (2001/10)
�P�@����Љ�
�@�P�T�N�O����V���K�|�[���ŕ�炷�V�[�g�E�K�q����́A���q����̏����b����f�@���Ă��炤���ߒ���I�Ɍ����a�@�ɒʂ��Ă���B�K�q����͍ō������N�̐���E�`���C��t���w�����A�f�@���͍Œ���N�̂S�{�����Ă���B���҂ɑ�������J���i�݁A�����a�@�ɋΖ������t�̏o�g��w�A�o���A���Â̎��сA�����Ă������p���m�F�ł��A��Â̑I�����ł��邱�Ƃ�]�����Ă���B
�Q�@��Ô�̃V�X�e��
�@�V���K�|�[������Â̎������߂����ŁA��Ô��Ⴍ�}���邱�Ƃɐ��������̂́A���f�B�Z�[�u�ƌĂ���Ô��p�̒��~���������Ô�������Ƃ����V�X�e���ɂ��B1984�N�A�����̎��[�E�N�A�����[�����u���ď����ł̌��N�ی��̔j�]�́w�l�̐ӔC�Ƃ������_���Ȃ��x���炾�v�Ƃ��A�u�����̈�Ô�͎����Ŏx�����v���Ƃ����A���@�Ȃǂɔ����Ă�����ςݗ��邱�Ƃ��`���t�����B�T�����[�}���̏ꍇ�A�����̂U-�W���������I�ɒ��~�B�����͊�Ƃ����S�B�ςݗ��Č��x�͂P�W�O���~�Ŕ�ېŁB�Q�D�T���̋����𐭕{���ۏ���B���̒��~�����͔�ېłő������\�B�܂���Ô�x�����Ȃ��l�ɂ͐��{�̓��f�B�t�@���h�����݂��Ă���B
�R�@�\�h�ӎ��Ƃf�o�ɂ���Ô�̐ߖ�
�@�����͈�Ô�������̒��~����x�������߁A�Ȃ�ׂ���҂ɂ�����K�v���Ȃ��悤�Ɂu���N�ł��悤�v�Ƃ����ӎ��������B����ɁA���{�͈�ʈ�(GP)�̖������d�����Ă���B�V���K�|�[���ł́A�a�C�ɂ��������ꍇ�܂���ʈ�ɂ�����A�K�v�ȏꍇ�ɐ�����Љ��̂��B�f�@���1��560�~�B���100�~�B�q�ǂ��ƍ���҂͂��̔��z�B�a�C�̑��������A�������Â�S����ʈ�ɂ͐[���m���ƖL�x�Ȍo�����K�v�ŁA���{�͂R�N�Ԃ̓��ʉے����}�X�^�[����悤���サ�Ă���B���̈�ʈ�̃V�X�e������Ô�̖��ʂ��Ȃ����ƂɂȂ����Ă���B
�S�@�����A�����a�@�̖���
�@�S�̂̂Q�����߂閯�ԕa�@�͂��t�����l�̍����T�[�r�X�Ŏw�����Ă���B���҂̑҂����ԃ[���A�Ǝ��̋~�}�Ԃ����L�A�Q�S���ԋً}�O���A�ڋq�T�[�r�X�ɓO�����E���ȂǁA�ꗬ�̌ڋq�T�[�r�X��S�����Ă���B�g�b�v�N���X�̘r�������������A�����a�@�Ƃ͈قȂ�f�@��͈�t�ɂ���ĈႢ�A���i�͎��R���ƂȂ��Ă���B���ψ�Ô�͌����a�@�̏�̃N���X�̖�Q�{�B������������Ύ��̍�����ÃT�[�r�X������B
�R�����g
�@�V���K�|�[���́A��Â̎��̍����ƈ�Ô��Ⴍ�}���Ă���_�ŁA��i�������璍�ڂ���n�߂Ă��܂��B�V���K�|�[���ł́A�������i�J�g�ܔ��Łj���������f�B�Z�[�u�ƌĂ���Ô��p�̎����̌����ɐςݗ��āi�����E���q�Ȃǂ̓_�ŗD���[�u����j�A���������Ô���܂��B���̂��߈�Ô�̐ߖ�A�a�C�̗\�h�ɓ��@�������N����܂��B�����ۂ����J���ꂽ���𗘗p���āA��p���S�ɉ����Ĉ�ÃT�[�r�X��I�ׂ܂��B��Ô��S�z���ȕ��S����Ό��ɓ����t���w���ł��܂��B�N���������Ɉ�Â����邱�Ƃ�O��Ƃ������{�Ƃ̈Ⴂ�͂���܂����A��Â̌��������l����ۂ̃q���g��^���Ă���鐧�x�ł��B�m�g�j�@�a�r�P�@�C���^�[�l�b�g�f�x�[�h�i01/09/29�j���܂Ƃ߂����̂ł��B(http://www.nhk.or.jp/debate
�Q�Ɓj
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�j���[�X�@�×{�^�a���Q�̐����x��A��Õی��ɂ��Љ�I���@�͉������ꂸ (2001/08
�j���[�X
�@�����J���Ȃ͍�N�l���̉��ی��J�n�ɂ��A���@���Ă���Q������̂��N��肪�މ@���A����𒆐S�ɉ��T�[�r�X���Ȃ����炷�p�^�[����z��B����܂ň�Õی��Řd���Ă����u���I�ȕ����v�̑��������ی��Ɉڍs����Ɗ��҂��Ă����B���̍팸���ʂ�2000�N�x��2.1���~�ƌ�����ł������A�V���P�V�����ۂ�1.7���~�������Ɣ��\���ꂽ�B
�@���̗��R�Ƃ��āA���ی��K�p�̎w������×{�^�a���Q�͍��N�l�����݂Ŗ�11.8�����Ɛ������x��Ă���A�܂����ی��{�݂ɓ�������ɂ͍��c���̗v���F��Ƃ����֖傪����B����ɑ���Õی��ł͋x�b�h������Γ��@�ł���P�[�X���������߁A�u�Љ�I���@�v����������Ă��Ȃ����Ƃ��l������B
�R�����g�F
�@�݉@�����Z�k�A�}�����a���팸�A�W���ÂȂǂɋ�̉�������{��ẪO���[�o���X�^���_�[�h�����A�K�����������łȂ��Ƃ����ł��B����Ƃ����͂ȁh�w���h���s����\������������܂��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�ݑ��Â͍��Ȃ��K�v���@�@�@�i���{�㎖�V��@No3963 00/04/08 p2-6)
�P�A�ݑ��ÂƂ�
�@�{�N�S������J�n���ꂽ���ی��ɂ����čݑ�P�A���d�������ƕ��s���āA�ݑ��ÂƂ�����Ì`�Ԃ����ڂ���Ă���B�ݑ��Â̎嗬�Ƃ��ĕ��y������K��f�ÂƂ́A�v��I�E����I�ɖK�₷�邱�Ƃɂ����퐶���̂Ȃ��Ōp���I�Ɉ�Îx�����s�����@�ł���A���҂̋��߂ɉ����čs���鉝�f�Ƃ����`�ԂƂ͊T�O�I�ɑ傫���قȂ�B
�Q�A���܍ݑ��Â����߂���w�i���q
�i�P�j���q����ɔ����v��썂��҂̑����Ɖ��̒������i���I���ی��̓����j
�i�Q�j��Ãj�[�Y�̕ω��[�����K���a��]���Ǐ�Q���ǂȂǂ̖����������̑����A�I����Â̕K�v���A�ƒ�i���퐶���j�ɂ�����p�n�k�̏d�v���̔F���[
�i�R�j��ËZ�p�̐i���ɂ��ݑ�ł̎��Ö@�̊g��
�i�S�j�V�l��Ô�̑�����}��
�i�T�j��t���̑����Ƃ��̊��ω��i�����f�È�̕K�v���j
�R�A�ݑ��Â̎��
���̓��e�ɂ��R�̎�ނ��l������B
�i�P�j�Ō���삪���S�̍ݑ��Ái�����������₻�̌��ǁj
�i�Q�j���Ҏ����ËZ�p��p����ݑ��Ái�_�f�A�l�H�ċz�A���S�Ö��h�{�Ȃǁj
�i�R�j�ݑ�����
�S�A�ݑ��Â̓���
�i�P�j��Ó��e�i�f�f�A�ώ@���x�A�}�ώ��̑Ή��Ȃǁj�͕a�@��ÂƔ�r���Ēቺ
�i�Q�j�Ώۂ͖�������Â̌p�����K��
�i�R�j�Ƒ��̕��S���傫��
�@�a�@��Â�����Ƃ�����ɂ��������Ƃ������z�͌��ŁA����ŕK�v�Ƃ�����Îx���ȉ����Ƃ������_�Ŋ��҃j�[�Y�ɉ������Ή����K�v�B�]���āA���ҁE��삷��Ƒ��E��Ã`�[���̗����E�A�g���s���ł���B���Ɉ�Ã`�[���ɂ�����l�������Ƃ��ẮA�ݑ�厡��ɂ�����I�K��f�ÁA����x���a�@�̊m�ہA�K��Ō�╟���T�[�r�X�Ȃǂ̎����̗L�����p�ł���B
�T�A�܂Ƃ�
�@�ݑ��Â�A�g�@�\��S����t�̃g���[�j���O���K�v�Ƃ���Ă���B�܂���Õی���A���@���Ԃ̒Z�k�����߂��Ă���A�}�������Ì�̑����ݑ��Â̕K�v���Ȃǂ��l������B
�R�����g
�@�@�ݑ��ẤA���҂���������ꂼ��̗�ňقȂ邽�߁A���x�̌ʐ��������Ă��܂��B��×ϗ��⊳�҂ƈ�Î҂̍��ӂ̘g���ŁA���L���}�g�́@�g���Ȃ��̂킪�܂܉^�т܂��h�@�̂悤�ȁA�n�ӁE�H�v���d�v�ł���Ǝv���܂��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�Y�ƂƂ��Ă̈���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ǔ��V���i2001/4/13�j
�܂Ƃ�
�@��Â��l�̍K����Љ�̈���� safety net �Ƃ��ċ@�\���Ă��܂����A�Y�ƂƂ��Ă��L�]�Ōٗp����Ȃǂɂ��𗧂��Ă���Ƃ������e�ł��B
�P�A��Ô�̑����ƈ�Õی��̊�@
�@�@������Ô�͑����̈�r��H��2000�N�x��29.1���~�A10�N���46���~�A25�N��ɂ�81���~�ɂȂ�Ƃ���Ă��܂��B���̐�i���Ɣ�ׂĂ�����قǍ����͂���܂���B�������o�ϐ������ȏ�ɖ��N���������Ă���A��Ð��x�̍��{�ł����Õی��������I�Ɍ������Ȃ��Ă��܂��B
�Q�A�Y�ƂƂ��Ă̈�Â̓���
�@�@�l���̍���ɂ͔ے�I�ȃC���[�W������A��Â���̖��͊�@���������Č���Ă��܂����A�V���o�[�Y�Ƃƌ�����悤�ɐ�������ł���Ƃ������ʂ�����܂��B��ÂɌg���l�ɂ͂�����ƌꊴ������ĕ������邩������܂��A�o�ϊw�̗��ꂩ��͈�Â͂ƂĂ��傫�Ȑ����Y�Ƃł��B�A�����J�́A1990�N��ɂ��Ȃ�ٗp�������܂������A��É�앪�삪�ˏo���ĐL�тĂ��܂��B80�N����́A��É��̌ٗp�͉����ƁA�^�A�E���v�ƂȂǂƓ���500���l�K�͂ł����B�Ƃ��낪�A���ł͉����Ƃ��A�^�A�E���v�Ƃ�700���l���x�ɂƂǂ܂��Ă���̂ɑ��A��É���1�疜�l�K�͂ɔ{�����Ă��܂��B��ÁA���Ȃǂ̎Љ�ۏ�̕���́A�������ƂƓ������炢�ɐ��Y�𑣂����ʂ�����܂��B
�R�A����̉ۑ�@�\��Ô�ƈ�Õی��\
�@�@��Ô�����邩��A�o�ς��������ނ̂ł͂���܂���B�Ⴂ�l�����̎Љ�ۏᕉ�S���傫���Ȃ肷���āA���͂������Ă���ƌ����Ă���l�͂��܂��B�������A������Ô�ƈ�Õی��̖��͋�ʂ��čl����K�v������܂��B��Õی��ɂ��Ă͌o�ϓI�ɗ]�T�̂��邨�N���͉����̕��S�����Ă��炤�A��Ô�ɂ��Ă͓��e���������A�S�̂ŗ}����Ȃǂ̉��v���K�v�ł��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
���ی��P�N�A���p�L�т��@
�@���ی����x�̒��ƂȂ�ݑ���T�[�r�X�i�ʏ���Z�����������܂ށj�̗��p���L�єY��ł���B�e�����̂����Ă����ی����ƌv��ɑ�����ۂ̗��p�����͑S�����ςłV�S���ɂƂǂ܂����B
�@���p���L�тȂ��w�i�ɂ͗l�X�ȗv��������B���ꌧ���Îs�́u�ݑ�T�[�r�X���{�݂𗘗p����X�����\�z��苭�������v�Ɛ�������B�Ⴆ�Α��{�����s�ł͓��ʗ{��V�l�z�[���̑ҋ@�҂���N�R���ɔ�ׂT�O�{�̂S�O�O�l�ɑ������B���p���L�єY�ő�̗v���͗��p�҂̈ꊄ�̎��ȕ��S�ƌ�����B�v���x���Ƃɗ��p���x�z����߂��Ă��邪�A���x�z�ɑ��闘�p���͍ł��Ǐy���v�x���łS�S���A�ł��d���v���x�T�łQ�V���������B
�@�����̂́A�v���F��Ȃǂ̎������S�������Ă���B���ɁA�v���F����U�������ƂɌ������_�ɂ͕s���������B�u�F�蒲������E����厡�ゾ���łȂ��A���p�Җ{�l�ɂ����S���傫���v�i�L���s�j�ƁA�v���F��̗L�����Ԃ̔p�~�⌴���P�N�Ԃւ̉��������߂Ă���B
�@�@�P�O������ی����̑S�z�������n�܂藘�p�҂̌o�ϓI���S��������A�ݑ�T�[�r�X�̗��p���т͂���ɉ�����\���������B
�@�@���p���т��v���菭�Ȃ��ꍇ�A�����͉̂��ی��̎��x�������ɂȂ邪�A����̂̓T�[�r�X���Ǝ҂��B�ݑ�T�[�r�X�������Ȃ��܂܂Ȃ瑽���̍ݑ�T�[�r�X���Ǝ҂͓P�ނ�����Ȃ��Ȃ�A���Ǘ��p�҂̑I�������܂�B���x���d���Ȃ�Ȃ�قǁA�ݑ���ł͌o�ϓI�ȕ��S���o�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��ߎ{�ݎu���͋��܂�A���ʗ{��V�l�z�[���͂ǂ����ҋ@�҂��ȑO��葝���Ă���B���͂�a�@�ɂ��Љ�I���@���ł����A��삪�K�v�ȍ���҂͍s���ꂪ�Ȃ��Ȃ鎖�Ԃ��N���Ă���B
�@�ی��������邱�ƂŃR�X�g�ӎ������܂�A�����҂Ƃ��Ă̎��o���萶����ƌ����Ă������A����͕��S�\�͂̂���l�����ɓ��Ă͂܂�B�m���ɕ��S�\�͂̂���w����́A����Ɍ������ی���������ׂ����낤�B�����A���S�\�͂��Ȃ��l�������ǂ����邩�Ƃ����Ƃ���ɉ��ی��ɉۑ肪����B
�@�@���T�[�r�X�̗��p�҂Ƃ��̉Ƒ���ΏۂɎ��{�����A���P�[�g�ł́A�u�Ƒ��̕��S�͌������v�Ɠ������̂͂R�R���B�u�ς��Ȃ��v���T�T���ōł������A�u���S���������v���P�Q���������B���ی��͂ł��邾���ݑ�ŗl�X�ȃT�[�r�X�𗘗p���Ȃ����삷��̂𒌂ɂ������x�B���������̕K�v�x�������قǁA���ی��̃T�[�r�X�x�����x�͈̔͂ōݑ���𑱂���͓̂���A�\���ȉ����悤�Ǝv���ƁA�o�ϓI���S���傫���Ȃ�B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�����a�@�E�×{���@�T�N�ԂłR�Q�{�݂��팸�@�@�@�@�@�@�@(01/04/26)�@
�@�@�W�U�N�A�����̍����a�@�E�×{���v�Q�R�X�{�݂��P�U�T�{�݂ɂ���ĕҌv�������B�X�X�N�ɂ͂���ɂP�R�{�݂��팸�Ώۂɉ����Čv�P�T�Q�{�݂ɂ��邱�Ƃ����߂��B�팸�Ώۂ̌v�W�V�{�݂̂����S�Q�{�݂����N�O���܂łɓ��p���܂��͌o�c�ڏ����ꂽ�B
�@�@�����J���Ȃ͓�\���A�팸�ΏۂƂȂ��Ă���c��̎l�\�{�݂̂����R�Q�{�݂ɂ��č���ܔN�Ԃœ��p���܂��͌o�c�ڏ�����Ƃ����v��̊T�v���܂Ƃ߂��B�R�Q�{�ݒ��P�T�{�݂͔p�~�A�P�V�{�݂͖��Ԃ̈�Ë@�ւȂǂɌo�c�ڏ�����B�c��P�R�{�݂ɂ��Ă��A�O�P�N�x���܂łɋ�̓I�ȍ팸��������@���l�߂���j�B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ��@�@�@
���I�a�@�̖�����
���߂�
�@�������a�@�ɋ߂�]�_�o�O�Ȉ�̊F����A���������̕a�@�̏����A�������r�I�߂������̕a�@�̍s�������l�������Ƃ�������ł��傤���B�L���҂̎��Z�ɂ��ƁA����̂܂܂ł�����2005�N����2006�N�ɂ܂��Љ�ۏᐧ�x������A�����ō��̍������j�]����Ƃ����Ă��܂��B���{�͂��̂悤�ȏ��ŁA��w�a�@�A�����a�@�𑶑����������ꂽ��@�Ƃ��ēƗ��s���@�l�����悤�Ə������Ă��܂��B���t�ł����͊ȒP�ł����A���܂łʂ�ܓ��ɐZ�����Ă�����w�a�@�A�����a�@���Ɨ��@�l�Ƃ��Đ����Ă�����ƐM���Ă���l�͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�S����200�����鍑���a�@�×{���ɂ��Ă͍����a�@�×{�����p���v�悪�i�߂��Ă��܂��B
���ԕa�@�̖�����
�@���݂́A���ł̍����a�@���L�ł̖��ԕa�@�������f�Õ�V�̓y�U�̒��ŋ������Ă��܂��B�������A��w�a�@�A�����a�@���Ɨ��@�l�Ƃ��ĕ⏕���̂Ȃ����E�ɓ����o���ꂽ�Ƃ��A���ԕa�@�͂قړ����y�U�ŋ����ł��邱�ƂɂȂ�܂��B���ԕa�@���^�ɐ����c���傫�ȃ`�����X���}���邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���̒��r���[�ȍ����j�]�œƗ��@�l����������ꂽ�Ƃ��A���ԕa�@�͋t�ɑ�ςȋ��n�Ɋׂ�܂��B���̍����j�]�����}���邱�Ƃ͕s�ސT�ł����A���̍����̈���������j�]�͖��ԕa�@�ɂƂ��Č����̍ۂɐ������_���̂悤�ɒǂ����ɂȂ邩������܂���B���̕s����Q������S�z����K�v�͂���܂���B���̍����̈����Ԉ�ÍĐ��̃`�����X�Ƃ���V�i���I��`���Ă݂����A���ꂪ���̎��_�ł��B
�Ζ���݂̍��
�@�}������ÂƖ�������Âɂ�����f�Õ�V��̋�ʂ��O�ꂷ��ƁA2010�N���炢�ł͂Ǝv���܂����A���݂����ʕa��126������50��������60�����܂ő啝�Ɍ�������Ɨ\������Ă��܂��B�����łɔ]�_�o�O�Ȉ�͉ߏ�C���ł��B�x�b�h���������ɂȂ����Ƃ��A������������Ζ��オ�����Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ł͍l�����Ȃ��]�_�o�O�Ȉ�̑厸�Ǝ��オ��������\��������̂ł��B21���I�͖��Ԃ̔]�_�o�O�Ȑ��a�@���L���ȗ���ɗ��ƍl�����A����]�O�ȋΖ���̖��Ԑ��a�@�u�������܂�\��������܂��B
�R�����g
�@���R�s�ő�c�L�O�a�@���o�c���Ă����c�����������̓��e���@�g�Q�P���I�ɂ�����]�_�o�O�Ȉ�Â̖��ƈÁh
�i�]�_�o�O�ȑ���@11(1):53-55, 2001�j�@���A�����I�ɂ܂Ƃ߂����̂ł��B�ǂ��Ӗ��ł������Ӗ��ł��C�ɂȂ���e�ŋL�^���Ă����̂ł����A�ǎ҂̔����͎^�ۗ��_�������悤�ł��B�薼�ł́g�]�O�ȁh�ł����A����ƌ��肹���ɁA�������R���̐܂�ɖ��ԕa�@���ǂ��߂炦�邩�̎��_����A�ᔻ�I�ɂ��ǂ݉������B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ��@
�}�������@��Âɂ�����DRG�^PPS�̖��_
�@�@�@�@�@�@�o���@�N�v�@���@�i��ʈ�ÃZ���^�[�������j�i����G��124�A��4��p523-526�A2000/08/15�j
�P�A�͂��߂�
�@�킪���̎Љ�ی���Ấu�o���������v�������Ƃ��Ă����B�ŋ߂ł͖������̈�Â�V�l��Â̒�z���������A������u�܂�ߕ����v���������X�Ɋg�債�Ă���A����ɂ��̕������}�������@���҂ɂ��L���铮��������B���̋�̗�Ƃ��ĕ���10�N11��1������A�}�������@��Â̒�z�����������A8�̍����a�@��2�̎Љ�ی��a�@�Ŏ��s����Ă���B���̒��Ԕ��\�ƌ����_�ɂ�������_���܂Ƃ߂��B
�Q�ADRG�^PPS�i��z�����j�����ƁA���̗��_�E���_
�@���̕����́ADRG�iDiagnosis Related Group�F�f�f�Q�ʎ������ށj�Ŏ������܂��ɕ��ނ��A���̕a���̂��������̎��Âɂ������p���z��������iPPS:
prospective payment system�j���̂ł���B����DRG�͈�Â̌o�ϓI������a�@�ԂŔ�r���Ė��_�������������Ì��������コ���悤�Ƃ����ړI�ō��ꂽ���A������z�����ɗ��p���邱�Ƃɂ��Ă͎�X�̖��_���w�E����Ă����BDRG�̗��_�Ƃ��ẮA��Ï�̖��_�����m�ɂȂ邱�ƁA�o�ϓI�ȊϔO����ÊW�҂ɐZ�����Ĉ�Â̖��ʂ��Ȃ��A�Ђ��Ă͈�Ô�̍팸�ɂ��Ȃ���_�ł���B���_�Ƃ��ẮA������Nj����邽�߂Ɉ�Â�����邱�Ɓi�������܂̎g�p����������A���@���Ԃ��ߓx�ɒZ�k�����j���l�����A���ۂɏd�ǎ҂��h�����Čy�ǎ҂�������Ȃ��Ȃǂ̖����N�����Ă���B
�R�A�{�M�ɂ����錻�݂܂ł̎��s����
�@���̎��s��5�N�Ԍp������邱�ƂɂȂ��Ă���B���݂܂ł̖��_�̑��́A����ɂ���Ď��Ö@�⎡�Ê��Ԃ���������ς�鍇���ǂ��f�f���ނŏd������Ă��Ȃ����Ƃł���B�����ǂ͕����ǁA�����ǂȂǂƂЂƂ܂Ƃ߂ɂȂ��Ă��邽�߁A�s�K�ȕ��ނɂȂ��Ă���B��2�̖��_�́A�����f�f�a�������Ă��Ă��A�d�Ǔx�ɂ���Ď��Õ��@���܂̎�ނ�ʁA���u���e�͓��R�ς���Ă��邱�Ƃ��l������Ă��Ȃ��B��3�̖��_�́A���҂����@��Z���ԂŎ��S�����ꍇ�ł���B���@���\������Z���ԂɂȂ��Ă��A�a�@�ɂ͈��z���x�����邱�ƂɂȂ�A�x�������ґ������̃V�X�e���ɂȂ�邱�Ƃ��K�v�ƂȂ邾�낤�B
�S�A�}�������@��Âւ̓����ɂ͐T�d��
�@�}�������@��Âł́A�ꕔ�o�����������c���A��z�����Ƃ̍œK�̑g������T��̂��悢�ƍl�����Ă���B���Ɏ�p���A�������͏o���������Ƃ��ꂨ��A��z�����Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���̂́A�摜�f�f�A��܁A�����A���@����w�Ǘ����A�Ō엿�A���@�����ł���B�܂���z����������ނ悤�Ȏ����A�O�Ȍn�ł����A�������A�l�a�w���j�A�A�������A�b��B�����A���������A�_�ΏǂȂǁA�����邱�Ƃ������ł���B�������A���t�����∫����ᇂȂǎ��Ö@�����݂���܂炸�A�܂��ω�������i�������҂����悤�Ȏ����̏ꍇ�ɂ́A��͂�o������������������K�v������B��ÂڂɌ���ŒS�����A���҂̗��v����闧��ɂ����t�Ƃ��āA�s���Ƃ͈�����ϓ_����咣���ׂ��ł��낤�B
�iAsahi Medical Sep. 2000 �ł́A���̒��Ԕ��\�͂��āA�݉@���Ԃ̒Z�k�ƂȂ炸�������Ă������b�g���ǂ݂Ƃ�Ȃ��Ɣ��f�A�h��ނ���}������Ò�z���̓����@�^�h�Ƃ��Ă܂Ƃ߂Ă���܂��B�j
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
����̐S���ڐA���ی��K��
�@�����J���Ȃ̒����Љ�ی���Ë��c��͓�\�ܓ��J��������ŁA����a�@�i���{���c�s�j�����{����]���҂���̐S���ڐA��p�ɂ��āA�����z��a�Z���^�[�i���s�j�Ɏ����ŁA��Õی��ň�Ô���ꕔ���S����u���x��i��Áv�̓K�p�����F�����B�S���ڐA�̓K�p���F�́A�Ώۂ͊g���^�S�؏ǂƊg�������^�S�؏ǁB�K�p�����ƁA����̓E�o��ڐA��p�Ȃǂ̔�p���S�Z�\���~�͎��ȕ��S�����A�f�@�⌟���A���@��p�͎��\�������ی��Řd����B�S���ڐA�͒ʏ�A��疜�~�ȏ�̔�p��������Ƃ����Ă��邪�A����܂ł̈ڐA�̔�p�͌�����Ȃǂł܂��Ȃ��Ă����B
�@�����c��͂܂��A��B��a�@�i�����s�j���s���]���҂���̊̑��ڐA��p�����x��i��ÂƂ��ė��������B�̑��ł͐M�B��A���s��Ȃǂɑ����{�ݖڂƂȂ�B���Ȃ́A�ܗ�ȏ�̈ڐA���s���Ă��邱�Ƃ����x��i��ÂƂ��ĔF�߂�����ɂ��Ă���B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�����Ȉ���@�@�@�@�@�@�@���{��t��C���^�[�l�b�g�f�C���[�j���[�X01/05/14�@��蔲���@
�P�A�����Ȋ�]�͂P�������F�u�Ζ���ρv�ƈ�w��
�@�����Ȃ�I�����悤�ƍl���Ă����w���̂U�N���͂P���ɂ����Ȃ����Ƃ��T���S���A�����J���Ȃ̌����ǂ̈ӎ������ŕ��������B�����Ȃ͖�Ԃ�x���̋~�}��Â��������ʁA�̎Z�����Ⴍ�A���q���̉e���������đS���Ŕp�~���������ł���B�c���ǒ��́u������Â͌������ł������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�R�|�T�̗c���̏��f���ȂNJ�{�f�×����R�����x�����グ�ҋ��ʂ����P������A�����₷�����������ď����Ȉ�𑝂₳�Ȃ��ƁA�����~�}��Ñ̐��͋߂���������v�Ƙb���Ă���B���������Q�O��w�̌v�P�R�P�U�l������B�������_�Ői�H�����߂Ă������̂X�U�����Տ����ڎw���Ă������A���̓���Łu�����ȁv�͂P�O���ɂ݂��Ȃ������B�u�����A�����Ȉ��I������\��������v�̂��Q�T���������̂ɑ��A�u�Ȃ��v�͂R�{�̂V�S���ɏ�����B�I�����Ȃ����R�́u���ɖ��͂�������Ȃ�����v���ł������A�u�Ζ�����ς����v�u�q���̎���ꂵ�ޗl�q���������Ȃ��v�u�q���̈�������ρv�u�̎Z�����Ⴂ�v�Ȃǂ��������B�����Ȉ�s���������������i�����j�ɂ��ẮA�U�W�����u�Ζ������̉��P�v���������B
�Q�A�w������Ȉ�m�ۂ֑�F�@�w���ɑi���A�������E���x��
�@���{�����Ȋw��i���`��j�͂T���S���܂łɁA�����Ȉ�̊m�ۂɌ����A�g�D�I�ȑ����邱�Ƃ����߂��B�e��w���ǂɁi�P�j���Ƃ⌤�C��ʂ��A��w���ɏ����Ȉ�̏d�v����ϋɓI�ɃA�s�[������i�Q�j������o�Y�ŗՏ��𗣂�鏗����t�����A���₷���Ȃ�悤�������P��}��\�Ȃǂ��|������j���B�@�����Ȉ�⏬���Ȃ�u���a�@�̌����ɔ����A��Ԃ�x���̏����~�}��Ñ̐��������ł��Ȃ��n�悪�����A�n�������̂���Ìv������������ł��x�Ⴊ�o�Ă���B�����J���Ȃ͏����~�}��Îx�����ƂƂ��āA�S�����珬���~�}�������������Ȉ�ւ̕⏕�����U�R�O�O�~�����グ�A�����Q�V�O�O�O�~�Ƃ����B��N�S���̐f�Õ�V����ł́A�R�Ζ������̓��@��{�����P��������P�O�O�O�~�A�b�v�i���ҕ��S�͂R�O�O�~���j���ĂR�R�R�O�~�ɂ���Ȃǂ̑������Ă��邪�A�s�\���Ƃ̐��������B���Ȃɂ��ƁA�����Ȃ���Ȑf�ÉȂƂ����t���͖�P�S�O�O�O�l�B�������N�͉�����Ԃ����A�J�ƈ�̍���⏗����t�̑ސE�Ȃǂ��d�Ȃ�A���ۂɓ����Ă��鏬���Ȉ�͌����C���Ƃ����B�����Ȃ�u���a�@�͂P�X�X�X�N�P�O���P�����݁A��R�T�O�O�J���łP�O�N�O�ɔ�ז�U�O�O�J�����������B
�R�����g
�@����҈�Â̏[�������{�̐��̍Č��ɓw�͂����l�B�ւ̎Љ�I�ӔC�Ȃ�A������Â̂���́A�i�e�ƂȂ鐢����܂߂��j����╟���Ȃǂ̊������Ƒ��܂��āA���{�̏����̐l�I�����琬�Ƃ����O�����̏d�v�ȉۑ�ł��B����̐��ڂ𒍖ڂ���K�v������܂��D
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�����K���a�̗\�h�ɓw�߂�z�K�����a�@�@�i�����h�N�^�[�}�K�W���@2001, 4���j
�L���v��
�@�@�z�K�����a�@�@�����c�����A���ł́w�����Ȃ��x�i�W�p�Ёj�̒��҂ƏЉ���ق����s���Ƃ�����X��������������Ȃ��B1964
�N�A����26�ňӋC����ŕ��C�����z�K�����a�@�́A�ݐϐԎ��S���~�A���҂͗��Ȃ��A��邱�Ƃ��Ȃ���Ԃł����B���̂悤�Ȓ��Œn��̏Z�������ƁA��炵�Ƃ������_���猒�N��g�̂��l�����D�̋@����܂����B�n��̐l�������]��ł�����́A���������ɋ��߂��Ă����Â���E���H���A�z�K�����a�@�̍Đ����X�^�[�g�����B
�@�u�w�₳�����x�Ƃ��������ŕa�@����������킯�͂Ȃ��A�a�C�������Ȃ���Ό�����������Ȃ��Ȃ�B�]�O�Ȃ�S���O�Ȃ��J�݂��A�K�v�Ǝv����V�������Ö@�A�V�����@���ϋɓI�ɓ������A�s��̃��x���ȏ�̈�Â����̐l���T���T��̒��i����s�j�Ŏ���悤�ɂ��Ă��܂��B���̂����ŁA�s��̑�a�@�ł͒u���Y���ꂽ���������Œ��J�Ȉ�Â��������Ă���̂ł��v
�@�@�u�ǂ�Ȃ��y�����ЂƂ�ŐH�ׂ�̂ł́A�����ɖO���Ă��܂��܂��B���̈�Â͈�t�ЂƂ肪�X�|�b�g���C�g�𗁂тĂ���B�ŏ��͊y�����ł��傤���A����Ȃ��̂͒����͂Â��Ȃ��B���҂���₻�̉Ƒ��ƈꏏ�Ɋ�ы������Ă����A��҂͈�ÂɊ�т�ւ����������̂ł��B��ËZ�p���}���ɐi�����钆�ŁA�i�ŋ߂̈�t�́j���̋Z�p���}�X�^�[���邱�Ƃ̂��X�ƂȂ�A����ȊO�̂��Ƃ�u���Y��Ă��Ă��܂����B��Ҏ��g���挊���@���Ă���̂�������܂���B�v
�R�����g
�@���쌧�͐����K���a�̗\�h�̐�i�n��ŘV�l��Ô���{��Ⴍ�A�܂����̖͔͗�Ƃ��Đz�K�����a�@���ǂ��m���Ă��܂��B����Ɋ֘A���āA��g�V���g�����K���a��h��
p63 �h�ł́g�ꎟ�\�h�̐��ʂ͈�Ñ��ɂ����v�������A�Ⴆ�ΐz�K�����a�@�̌o�c�͍����ɂȂ��Ă���h�Ƃ����L�q������܂��B���p�̑O���������^���Ȃ�D�܂�������ł����A�\�h�ƌ��s�̐f�Õ�V�̌n�Ƃ̖����������Ă��܂����B
�@���_�́A�g�����K���a�̗\�h�⒚�J���ɗ͂�����Ă��邪�A�����o�c�͍ŐV��w�̓����ɂ����́h�ł����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�