�@���a����i�����K���a�ȂǁA�a�C�ɂȂ�Ȃ��w�́j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2001�N7��1���쐬�@2004�N3��1�������j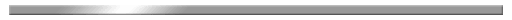
���e
�얞���ӓ|�ɍčl�@�|�j���͂₹�̕������S���������[�@�i2002/06/19�j
�l�ԃh�b�N��f�ғ��v�@�@�������Ȃǂ̑����~�܂�@�@�@�i2003/08/26�j
�R���X�e���[���Ɠ����d���@�|���̗\�h�Ǝ��Á[�@(2001/10)�@
�����K���ɒ��ڂ������a��̊�{�I������
�������ɂł��鐶���K���a�̗\�h�̈���@�@
�������đO�����ɕ�炷
�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
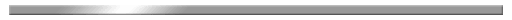
�얞���ӓ|�ɍčl�@�|�j���͂₹�̕��������S���[�@�i2002/06/19�j
�@�����J���Ȍ����ǂ��S���̖�41,000�l��Ώۂɂ����ǐՒ����ŁA���{�l�̒��N�j���͕W���I�ȑ̏d��葾���Ă��Ă��₹�Ă��Ă����S�����オ�邪�A�j���͔얞���₹�̕����W�c�̎��S���㏸�̑傫�ȗv���ɂȂ�Ɣ��\�����B�j���͑̏d�̎w�W�ł���BMI�i�̊i�w���j�ŕW���I�Ƃ����l��菭�����߂̕������S�����Ⴂ���Ƃ��������A�얞�ւ̒��ӂ����ɌX�������Ȍ��N��ɁA�čl�𔗂錋�ʂƂȂ����BBMI�́A�̏d�i�L���j��g���i���[�g���j�̂Q��Ŋ������l�ŁA�̏d70�L���Őg��1.7���[�g���Ȃ�a�l�h��24.2�ƂȂ�B�W����22�ŁA25�ȏオ�얞�Ƃ����B
�@�H�c�A����A���ꌧ����40-50��̒j����Ώۂ�10�N�ԒǐՒ��������B�j���ł́ABMI��23-24.9�̐l�̎��S�����ł��Ⴉ�����B���̐l��������ɂ���ƁA21-22.9�̐l��1.3�{�A19-20.9�̐l�ł�1.6�{�ƁA�]�܂����Ƃ���Ă���BMI�l�ł����S���͍����Ȃ����B������ł��A25-26.9�̐l��1.1�{�A27-29.9��1.4�{�Ǝ��S���͏��X�ɍ��܂������A�₹�ɔ�ׂ�ƌX���͊ɂ₩�������B�j���ɂ��āABMI�̊e�O���[�v�ʂ̐l���̊����́A23�����̐l���S�̂�44�����߂��B25�ȏ�̐l��28���ŁA���S���㏸�̓_����́A�₹�̕����d�v�Ȗ��ƕ��������B
�@�����ł�BMI
19-24.9�̐l�̎��S�����Ⴂ���A19������25�ȏ�̐l�͒j�����l�A���S����2�{�߂����������B
�R�����g
�@���v�Ɋ�����V���������ł��B�ł��g�j���Ń_�C�G�b�g�ɔM�S������͍̂�����́h���x�̃C���p�N�g�ł��傤���H
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�l�ԃh�b�N��f�ғ��v�@�@�������Ȃǂ̑����~�܂�@�@�@�i2003/08/26�j
�@����15�N8��26���̓��{�a�@��\�h��w�ψ���̔��\�ɂ��A2002�N�ɐl�ԃh�b�N����f�����l�̂����A�����K���a�ƊW�̐[���������E�̋@�\�ȂǂɈُ킪�������l�̊����͑O�N���݂ŁA���͂��n�߂�1984�N����̑����X���Ɏ��~�߂����������B�ψ���ł́u�����K���̉��P�̎w�����悤�₭���ʂ��o���Ă����v�Ƃ��Ă���B
�@���͂����͎̂�f��284���l���B�����K���a�Ɗ֘A�̐[��6���ڂł́A�̋@�\�ُ�26.1���A���R���X�e���[��24.4���A�얞21.0���A������14.3���A���������b14.2���A�����l�ُ�11.9���ŁA�O�N�ɔ��0.7��������1.0�����ƁA�قډ����������B
�@�������ڂ��ׂĂ��u�ُ�Ȃ��v��13.3���i�j��11.7���A����15.9���j�Ɖߋ��ň����������A���ψ���́u�������ڂ����������߂ŁA�S�̂Ƃ��Ă͉��P�X���v�Ɛ������Ă���B�]���ƈقȂ�A�n�捷�͂قƂ�ǂȂ��Ȃ����B�܂��A�l�ԃh�b�N�Ō�����������́A�������Ɉ݂���A�咰����A�x����ŁA�j���͑O���B�������A�����͓����ő��������B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�R���X�e���[���Ɠ����d���@�@�\���̗\�h�Ǝ��Á\�@�@(2001/10)
�܂Ƃ�
�@�@�����Đ��l�a�Ƃ���ꂽ�����K���a�̒��ŁA�S�؍[�ǂƔ]�����̌����ł��铮���d���ɂ��āA���o�Ǐ�Ȃ��i�s���邽�ߎ����̌����R���X�e���[���l�ɒ��ӂ��邱�ƁA�\�h�̂��ߐH����^���ɋC�����邱�ƁA���Â��i�����Ă������ƁA�Ȃǂ��q�ׂ܂��B���{�o�ϐV���i2001/09/29�j�́g���o���N�V���|�W�E���h���܂Ƃ߂����̂ł��B
�P�@�����d���͎��o�Ǐ�Ȃ��i�s����
�@�����d���͏\��A��\�ォ�珙�X�ɐi�s���܂��B���������ꂪ�N��ɉ����������I�͈͂��Đi�s����ꍇ������A���nja�����Ƃ��Ƃ� 25�@���ɂ܂ōׂ��Ȃ��Ă��ɂ����y�����Ȃ��̂����ł��B
�Q�@�����d���𑣐i����R���X�e���[���ƍ�����
�@���t���̃R���X�e���[���Ɗ����_�f�������d���ɊW���܂��B�R���X�e���[����S�g�̍זE�ɉ^��LDL�����߂�����A�]���ȃR���X�e���[�����̑��ɉ������HDL�����ȉ߂���ƃR���X�e���[���������ǂɂ��܂�A���ꂪ�����_�f�ɂ��炳��Ď���ɓ����d�����N����܂��B���̂悤�ȍ������LjȊO�ɁA�������ⓜ�A�a�A�܂������얞�A�i���A��`�I�v���A�X�g���X�ߑ��A�^���s���A�H�����̗���Ȃǂ������d���̑��i�v���ł��B���{�����d���w��ł��߂��������ǂ̊�́A���R���X�e���[��220�r�^?�ȏ�A�k�c�k�R���X�e���[��140�r�^?�ȏ�����R���X�e���[�����ǁA�������b150�r�^?�ȏ�����������b���ǂƂ��Ă��܂��B�܂�HDL�R���X�e���[����40�r�^?�������HDL�R���X�e���[�����ǂƂ��Ă��܂��B�i���F�k�c�k�����R���X�e���[���[�g�c�k�[�s�f/�T�iFriedewald�̌v�Z���j�j
�R�@�����d�h�̗\�h�Ǝ���
�@�����d����\�h���邽�߂ɂ́A�����K�����������A���P���邱�Ƃ��K�v�ł��B�H�����H�v���A�K�x�ȉ^�����K���Â��A�������x�{���\���ɂƂ�܂��B�����̓w�͂ł��������ǂ����P����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�Ǐ�E�̎��E���̊댯���q�Ȃǂɉ����A���Â��K�v�ƂȂ�܂��B
�P�j�@�H���̍H�v�@�\���b�̉ߏ�ێ�ƐH���@�ەs���\
�@�������ǂ̗\�h���猩��ƁA���{�l�̐H�����ɂ͂Q�̖�肪����܂��B��1�͎��b�ێ�ʂ��K���͈͂��Ă��邱�Ƃł��B�Ⴆ�Ύ��b�͓��A�A���A������S�T�P�̊����Ŏ��̂��D�܂����Ƃ���Ă��܂��B�I���[�u���Ȃǂɑ����܂܂�Ă���ꉿ�s�O�a���b�_�̃I���C���_�ɂ́ALDL�R���X�e���[�������炷�����ɁA�_�����ɂ����Ƃ�������������܂��B�܂��m�َq�A�y�X�g���[�ނ͈ӊO�ɑ����̎��b���܂�ł��܂��B��2�̖��_�́A�H���@�ۂ̐ێ悪�s�\���Ȃ��Ƃł��B�H���@�ۂɂ̓R���X�e���[����ΊO�ɔr�o������A���b�̋z���⒆�����b�̍�����}������ȂǁA�l�X�ȓ���������܂��B���C���A�L�m�R�ނ��܂�ׂ�Ȃ��H�ׂ邱�Ƃ���ł��B���Z�������ɂ͔[�����肨���̂���҂�A�L���E����g�}�g�A�o�i�i�P�{�A��W���[�X�P�t�ł������ł��傤�B
�Q�j�@�^��
�@�������ǂ̗\�h�ɂ͓K�x�ȉ^�������ɗ����܂��B�^���ɂ�HDL�R���X�e���[���𑝂₵�A�������b�����炷���ʂ�����܂��B���Ɍ��ʓI�Ȃ̂́A�E�H�[�L���O���͂��߃W���M���O�A�T�C�N�����O�A���j�␅���^���A�G�A���r�b�N�_���X�ȂǁA�_�f���\���Ɏ�荞�݂Ȃ���A���ꂹ���ɒ����Ԏ����ł���L�_�f�^���ł��B�^���̋����̖ڈ��͖ڕW�S�����������鋭�����ǂ��Ƃ���܂��B�ڕW�S������220����N��ƂP���Ԃ̈��Î��S���������������l��0.4����0.6�{���A����Ɉ��Î��S������������Əo�Ă��܂��B���̒��x�̉^�����P��R�O������P���ԁA���T�R�A�S��s���Ƃ����ł��傤�B�P���̉^�����Ԃ��P�O�������ɕ����āA����������Ă����l�ł��B
�R�j�@����
�@���R���X�e���[���l��LDL�R���X�e���[���l�������ꍇ�̓V���o�X�^�`���Ȃǂ�HMG�]COA�Ҍ��y�f�j�Q��1�I���Ŏg���܂����A�������b�l�������ꍇ�̓t�B�u���[�g�n��j�R�`���_�n�̖悭�g���܂��B����ɒ����I�Ȏ���ɂ����Č��ǂ���鎡�Ö@������܂��BHMG�|COA�Ҍ��y�f�j�Q���A�A���W�I�e���V���ϊ��y�f�j�Q��E�A���W�I�e���V���U��e�̝h�R��Ȃǂ̍~����ł��B�����̖�͒P��LDL�R���X�e���[���⌌���������邾���łȂ��A�����d���̐i�s��h������A�y�x�̓����d����ޏk�������p�����邱�Ƃ��������Ă�������ł��B
�S�@�Ō��
�@���{�l�̕��σR���X�e���[���l��1990�N�ɃA�����J�l�̕��ϒl�ɒǂ����Ă��܂��A�����͋������S������]���Ǐ�Q���}�����鋰�ꂪ����܂��B��l�ЂƂ肪���ȐӔC�����Ɋ�Â��Đ����K���ɋC�����A�R���X�e���[���⌌���̊Ǘ�����������s�����Ƃ��K�v�ł��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�����K���ɒ��ڂ������a��̊�{�I�������@�@�@�@�i�����ȃz�[���y�[�W���甲���@2000/12�j
�P�@�͂��߂�
�@���l�a��́A���a�R�O�N��ȍ~�A�]�����A����A�S���a�̂�����R�听�l�a�𒆐S�Ƃ��Ċe��̎{�u�������̐��ʂ��B����́A���a�ʂɖ��炩�ɂȂ��������K���Ƃ̊֘A���W�A�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��u����v�Ƃ����v�f�ɒ��ڂ��ėp�����Ă����u���l�a�v�ɑ����āA�\�h�\�Ȑ����K���Ƃ����v�f�ɒ��ڂ��ĂƂ炦�����āA����̎��a�����w���i����K�v������B
�Q�@���l�a�y�ё�̌���
�@�@�@�ȗ�
�R�@���a�̗v���Ƃ킪���̐����K���̌���y�щۑ�
�i�P�j���a�̗v���Ɛ����K��
�P�@���a�̗v���Ƒ�̂����
�@��`�q�ُ̈�������܂߂��u��`�v���v�A�a���́A�L�Q�����A���́A�X�g���b�T�[���́u�O�����v���v�A�H�K���A�^���K�����͂��߂Ƃ���u�����K���v���v�����܂��܂ȗv�������G�Ɋ֘A���Ď��a�̔��Njy�ї\��ɉe�����Ă���B�܂��A����u�����̂��l�����ꍇ�A�u��`�v���v��u�O�����v���v�ɑ��Ă͌l�őΉ����邱�Ƃ�����ł������A�u�����K���v���v�ɑ��Ă͐H�K���̉��P��K�x�ȉ^���A�����E�i����Ȃnjl�ł̑Ή����\�ł���B
�Q�@���N�Ɛ����K��
�@���N�Ɛ����K���Ƃ̊W�ɂ��ẮA���łɈȉ��̂V�̍��ڂ̒��Ŏ��{���Ă��鐔�̑����҂قǕa�C�ɂȂ炸�A�܂������������������Ƃ����炩�ɂȂȂ��Ă���B�@�K���Ȑ������ԁA�@�i�������Ȃ��A�@�K���̏d���ێ�����A�@�ߓx�̈��������Ȃ��A�@����I�ɂ��Ȃ范�����X�|�[�c������A�@���H���H�ׂ�
�A�@�ԐH�����Ȃ�
�i�Q�j�����̐����K���̌���i�����U�N�u�����h�{�����v����j�y�щۑ�
�P�@�h�{�ێ擙�ɂ��āF�ȗ�
�Q�@�H���ێ�ʂɂ��āF�ȗ�
�R�@�^���K���ɂ���
�@�^���K���̂���l�i�^�����T�Q��ȏ�A�P��R�O���ȏ�A�P�N�ȏ�p�����Ă���l�j�̊����́A�e�N��ɂ����đ����X���������Ă�����̂́A�S�̂ł̉^���K���̂���҂͂R�O���ȉ��ł���B
�S�@�����K���ɂ��āF�ȗ�
�T�@�i���K���ɂ��āF�ȗ�
�S�@�u�����K���a�v�Ƃ����T�O�̓����ɂ���
�i�P�j �����K���ɒ��ڂ������a�T�O�̓����̕K�v��
�@�u���l�a�v�Ƃ����T�O�́A����Ƃ������ۂ͂�ނȂ����̂ł���A���̔N��ɂȂ����i�K�ő��������E�������Â��s�����Ƃ����ʓI�ł���Ƃ����F�����������Ă��Ă���A�����̌��f�ɑ����f�s���𐄐i�����ő傫�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃ́A�]�������ׂ��ł���B
�@����A�O�q�����悤�ɁA�����K�������P���邱�Ƃɂ�莾�a�̔��ǁE�i�s���\�h�ł���Ƃ����F���������ɏ������A�s���Ɍ��т��Ă������߂ɂ́A�V���ɁA�����K���ɒ��ڂ������a�T�O�����A���Ɉꎟ�\�h������͂ɐ��i���Ă������Ƃ��̗v�ł���B����ɁA���a�̜늳�ɂ��p�n�k�̒ቺ���\�h�����ƂƂ��ɁA�Ђ��ẮA�N�X���傷�鍑����Ô�̌��ʓI�Ȏg�p�ɂ���������̂ƍl������B�@�A���A�u�a�C�ɂȂ����̂͌l�̐ӔC�v�Ƃ����������⊳�҂ɑ��鍷�ʂ�Ό������܂�邨���ꂪ����Ƃ����_�ɔz������K�v������B
�i�Q�j �����K���ɒ��ڂ����p��̗�
�@�@�ȗ�
�i�R�j �u�����K���a�v�̒�`�@
�@����A�u�����K���a�ilife-style related diseases�j�v�Ƃ����ď̂�p���A�u�H�K���A�^���K���A�x�{�A�i���A���̐����K�����A���̔��ǁE�i�s�Ɋ֗^���鎾���Q�v�ƒ�`���邱�Ƃ��K�ł���ƍl������B
�T�@����̎��a��ɌW�錟���ۑ�ɂ���
�i�P�j �ꎟ�\�h�̐��i
�@�m���̕��y�����ł͕K�����������K���̉��P�Ɍ��т��Ƃ͌���Ȃ��̂ŁA����@�̉��P�݂̂łȂ��A�Љ�I�ȕ�����A�K�������̐��i�A�H�i�̉h�{�����\���A���N���i�{�݂⌒�N�ۗ{�n�̐����ȂǁA�l�ł̑Ή����@�@���ł͂Ȃ��A�ނ���Љ�S�̂Ƃ��āA�u�����K���a�v��\�h���邽�߂̊��@�����邱�Ƃɂ��Ă���������K�v������B
�i�Q�j�@���ʓI�ȓ\�h��̎��{
�@����́A���f�̈Ӌ`�A��p�Ό��ʁA�l�̑I�𐫂Ȃǂ̊ϓ_����A���[���������f�T�[�r�X�̒̐��⌟�f���ʂɊ�Â������K�����P�w���̏[���ɂ��Ă���������K�v������B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�������ɂł��鐶���K���a�̗\�h�̈���@�@�@�|���N�Ǘ��Ɖ^���K���[�@�@����G���ւ̓��e
�@���̕��͂́A�쐼�s���[���e�j�X�N���u�̉��Ɍ��N�Ǘ��ɂ��ď��������̂̓]�ڂł��B�����K���a�̗\�h�Ƃ������_�ŁA���N�Ǘ��Ƃ���ɖ𗧂^���K����ʂɂ��ďq�ׂ܂����B��g�V���h�����K���a��h���h�A�i���j�����Ȃ̃z�[���y�[�W���Q�l�ɂ��܂����B�@�@�i�Q�O�O�O�N�P�Q���j
�P�A�����K���a�ƈꎟ�\�h
�@�ŋߐ����K���a���������t�����ɂ���悤�ɂȂ�܂����B�ȑO�́A�S�O���z�����N��ɑ����]�����A����A�S���a�Ȃǂ𐬐l�a�Ƃ��āA�W�c���f�ő����ɔ������i�ŋ߂͂����\�h�ƌ����܂��j���Â�����i�s���Ƃ߂邱�Ƃ���Ƃ���Ă��܂����B�����������̕a�C�̔��a�ɂ͔N����`�Ƃ����������邱�Ƃ��s�\�ȗv�f�ȊO�ɁA����̓w�͂ʼn��P�ł��鐶���K�����[���֗^���邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B�܂����a���Ă���̎��Âł͐����̎�����X�̒��x�ɒቺ����ꍇ���������ƁA����Љ�ł͈�Ô�����Ĕj�]�����˂Ȃ����ƂȂǂ���A�����K���̉��P�ɂ��a�C�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ���ꎟ�\�h�Ƃ����l�����łĂ��܂����B�������Ȃ��u���l�a�v����A���a���Ȃ��悤�ɍH�v����u�����K���a�v�ɁA�a�C�̊T�O���������ēw�͖ڕW���قȂ��Ă��܂����B
�Q�A��\�I�Ȑ����K���a�ƌ��N�Ȑ����K��
�@����A�]�����A�S���a�A�t���a�A���A�a�Ȃǐ����K���a�ɂ�鎀�S�Ґ��͑S���S�Ґ��̖�U�R�������߂܂��B�܂����Ґ��͑������Ă���A�������ǂU�S�O���l�A�S���a�P�U�P���l�A���A�a�P�T�V���l�A�]�����P�S�Q���l�Łi����͖��������Ȃ����ߊ��Ґ��Ƃ��Ă͔�r�I���Ȃ��j�A���Â��Ă��Ȃ��l���܂߂�ƁA�������͖�R�S�O�O���l�A���A�a��T�O�O���l�Ɛ��肳��Ă��܂��B��ʐf�È�Ô��������Ô�̖�R�T���ɂ̂ڂ��Ă��܂��B���N�i�������⌒�N�����i��������Q��������Ԃ����������ԁj����������D�܂��������K���Ƃ��āA��i���A����ߐ��A�������H�ێ�A�K���Ȑ����i�V�[�W���ԁj�A�K���̏d�ێ��A����I�^���K���A�ԐH�����̂V���ڂ��m���Ă��܂��B�����̌X�̍��ڂɂ��ẮA�Ⴆ�Ή����⎉�b�ێ�ʂ̌����K���l����ɂ͉��P�ɂ��̏d�ւ̉e���ȂǏڍׂȕ�����Ă��܂��B�����ł́A�^���K���Ɍ����ďq�ׂ邱�Ƃɂ��܂��B
�R�A�^���K���Ƃ�
�@�����̉^���K���̌���Ƃ��āA�h�^���K���̂���l�i�^�����T�Q��ȏ�A�P��R�O���ȏ�A�P�N�ȏ�p�����Ă���l�j�̊����́A�e�N��ɂ����đ����X���������Ă�����̂́A�S�̂ł̉^���K���̂���҂͂R�O���ȉ��ł���B�h�ƕ���Ă��܂��B�^���s���͔얞�A���A�a�A�S���a�A���e頏ǂȂǂ̌����ƂȂ�܂��B������h���ɂ͗L�_�f�^���i�G�A���r�b�N�X�j�Ƃ��鎝�����̉^�����D�܂����A�Z�������̂悤�Ȍ������^���͐S�x�@�\�̌���ɂ͌����Ă��܂����A�����̏���������b�̏�����Ȃ����ߐ����K���a�̗\�h�Ƃ����ړI�ɂ͓K���Ă��܂���B��ʂɗL�_�f�^���̗ʂ͉^�����x�Ɖ^�����鎞�ԂƂŌ��܂�܂��B�^�����x�͖����Ő��肵�܂����A�K�x�ȋ��x�i�ő�^�����x��50���ɑ����j�͈��Î��̖������i����70/�b�Ƃ��܂��j��120�i40�Α�j�A115�i50�Α�j�A110�i60�Α�j�ɑ��������ԂƂ���Ă��܂��B�܂��K�x�ȉ^�����Ԃ́A�P�T�Ԃ̍��v�ł��ꂼ��160�A150�A140���ŁA��������ɏ��Ȃ��Ƃ�10���ȏ�A����̍��v���Ԃ�20���ȏ�A�����Ƃ��Ė���������̂��悢�Ƃ���Ă��܂��B��̖ڈ��Ƃ��Ĉ��20�[30���A���߂ɕ����̂��悢�Ƃ���Ă��܂��B
�S�A�ꎟ�\�h�^���̖��_
�@��ʂ̕a�C�͒ɂ݂┭�M�Ȃǂ������Ď����I�Ɏ�f����킯�ł����A�����K���a�́i���̏����ɂ͍��R���X�e���[�����ǁA�������A�������Ȃnj�����ُ̈�͌�����܂����j�����ɂȂ�܂ʼn��̋�ɂ�����܂���B�܂��ꎟ�\�h���d�v�ł��邱�ƂƁA��������H���邱�ƂƂ͓����ł͂���܂���B����N�͕B���N�ɂ��߂ɂ͎���ł�������Ƃ������M�҂͗�O�Ƃ��āA
�ꎟ�\�h�ƍ��v���Ȃ��h�s���N�ȁh�����K����ǂƂ���l������̂������ł��B�����I�ȉ��ď����ł͊���10�N�ȏ�O���琶���K���a�̊T�O�����Ď��ȊǗ��𑣂��Ă��܂��B���̓��@�t���Ɉ�Õی���Ђ̎w��������ی����̍��ʉ��A�����̒l�グ�A���N�H�i�̕t�����l�ŖƏ��Ȃǂ��s���Ă��܂��B���{�ł́A�O�H������A���ށE�����E�������E�َq��40�����炷�A�O�H�E������������30�����炷�A�^���̂��߃o�X��Ԃ��T���ĕ����A�Ȃǂ̈ꎟ�\�h�ɓw�߂�Ήƌv�ŔN��40���~�̐ߖ�ɂȂ�Ƃ������Z������܂��B
�@�����̓��@�t�������{�l�ɓK���Ă��邩�ǂ����͋^�₪����Ƃ���ł��B�������U����W���M���O�̗����A���N�H�i��~�l�������[�^�̏���̑����A�����̐�s���Ȃǂ̃g�����h���݂�ƁA���N�͎����œw�͂��đ��i������̂Ƃ����ӎ����L�܂��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B
�T�A�Ō��
�@�@���̉^���K���͏T�Q����x�̃e�j�X�ƃW���M���O�ɂ��܂��B�l�I�ɂ́A�فX�Ƒ���W���M���O�Ɣ�ׂāA�Q�[���̗v�f�E�v���[�̍��Ԃ̑Θb�E���ꂪ��莝�������Ȃǂ����������e�j�X�́A�́i���`�̌��N���i�j�A�S�i�X�g���X�����j�A���i�ڂ��h�~�j�����S�����āAmature
age ��S������̂ɗL�v�ȉ^����ڂ̈�Ǝv���Ă���܂��B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�������đO�����ɕ�炷�@�@-�V���̑̌��L-�@�@�@�@�i���o2000/08/06�@�L�������j
�܂Ƃ�
�@�V�N��w�̌����҂ł�����96�̏���i�O�_���a���j���A���g�̌o�������ƂɌ�����g�V���̑̌��L�h�ł��B���ۂ����K�����������������A�H���͉h�{�o�����X���l���A���ׂȂǂ͑��߂Ɏ蓖���Ă����点�Ȃ��A�Ȃǂ̍H�v����Ƃ������e�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@90�ň�Â̑��킩�犮�S�ɑނ��A���݈�l��炵�ŏT���a�@�ɏo���Ă���B����܂Ŋ��҂ɘb���Ă���������̒��ӓ_���A�������g���S�����Ă���B�V���̃v���Z�X�͐獷���ʂł��̘b���N�ɂ����Ă͂܂�킯�ł͂Ȃ����A���ꂩ�獂������}����50�A60�Α�̐l�B�Ƃ��̉Ƒ��Ɍ����āA�V���̎x�x�̎Q�l�ɂȂ�悤�ɂ܂Ƃ߂��B
�P�A���l�ɗ��炸�A�������Đ����Ă�������
�@�����́g���Ԋ��h�����߂āA���邾������ɂ����ĕ�炷�B�z�c�̏グ���낵�A�H���̎x�x�A�ˊO�̑|���Ȃǂ�̗̓`�F�b�N�Ƃ݂Ȃ��A���ꂪ�ł���Α��v�Ɣ��f�B�킴�킴�z�e�������̃p�����ɍs���A�ł��邾���^�N�V�[�ɏ�炸�ɓd�Ԃňړ�����ȂǁA�̂��Ȃ܂�Ȃ��悤�ɍH�v����B�Љ�I��ɊÂ��������炩�����ĘV������ł��܂��B�����̎c���\�͂����ɂ߁A�ł���͈͓��Ŏ�������������S������B�t�ɎႢ����ɂ́A�ߕی�Ȉ����������悤�Ȕz�����˗��B
�Q�A�h�{�o�����X�̎�ꂽ�K���������H��
�R�A��ꂪ���܂�Ȃ��悤��
�@�s�f���猈���Ė��������Ȃ����ƁB�܂����C���������瑁�߂Ɏ蓖����B�g�����h�ɑΉ�����̂���B
�S�A�O�����ȋC�������ێ����Đ����ɒ����
�@�a�̂ɒ��킵�ē��e���Ă���B�����Ɣo��̉������Ă���B���������ƕ�炷���߂ɂ́A��ɉ�������Ă݂�悤�ȑO�����̋C�������厖�Ǝ�������B
�T�A�܂Ƃ�
����҂͍ƂƂ��ɓ������݂��Ȃ��Ă������A�������ƌ����ĉ�ݔ��𐮂�������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B�������g�̂��Ƃ��l�����ꍇ�A�������đO�����ɐ�����C���������邩�炱�����ĕ�炵�Ă�����̂��Ǝ�������B�ߕی�Ȋ������A�c�����͂�D���悤�Ȃ��Ƃ͔�����ׂ����B
���e�i�ڎ��j�ւ��ǂ�
�g�b�v�y�[�W�ւ��ǂ�